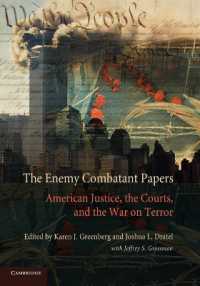出版社内容情報
次々と銀座で大規模再開発案が浮上した2003年以降、商店街はどのように結束し、企業や行政と街の未来を話し合ったのか。全国商店街も参考にできる、しなやかなまちづくりを紹介。
内容説明
二〇〇三年夏、松坂屋と森ビルによって、二百メートル近い高さの超高層ビル計画が銀座に提案された。しかし、本当に超高層ビルは必要なのか?小ぶりだが一流専門店が揃った街並み、回遊性の高い区割りなど、「銀座らしい」まちのにぎわいを守るため、商店街が結束し、地域のルールを考えはじめた。地域のまちづくりは地域で考える―未来の銀座のあり方を模索した十数年の活動を追う!
目次
プロローグ 銀座に超高層ビルが計画された
第1章 銀座とはどんな街か
第2章 大規模開発前夜、九〇年代の銀座―第一次地区計画「銀座ルール」の策定
第3章 二百メートルの超高層ビルが銀座に?―「銀座街づくり会議」をつくろう
第4章 銀座の声を行政へ!
第5章 新建築は銀座との事前協議が必要に―銀座デザイン協議会の船出
エピローグ ふたたび松坂屋の再開発について
著者等紹介
竹沢えり子[タケザワエリコ]
東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。銀座街づくり会議・銀座デザイン協議会事務局長。2011年、東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程修了。博士(工学)。博士論文にて日本都市計画学会論文奨励賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ja^2
4
確かに私も、銀座は今のままであって欲しいと思う。空が大きく見えるのが銀座—その通りだ。▼だが私は本書を読んで、むしろそうした思いは風前の灯のように感じてしまった。なぜなら、ここで紹介されている歌舞伎座の超高層を許した理屈や、銀座三越などで廃道を認めた理屈にまったく説得力を感じなかったからだ。▼恐らく銀座も内部崩壊するのだろう。これまでのように大資本を敵としているうちは良いが、地権者自らがより収益性を求め始めれば、それに反対することはできないに違いない。▼その時にボクの思い出を壊すなと言っても始まらない。2014/06/03
RYU
2
銀座の街並みを守る取組みの記録。様々な相反する価値観が同居する銀座は、1612年に銀貨鋳造所が設置されらことに起源を持ち、1872年の明治大火後に西欧を模した街並みに一変、大震災や戦災を経つつも、文化人や商人が集い、また入れ替わりながら発展してきた。1963年の容積率規制開始によって既存不適格建物となった建物の建替を可能とする地区計画「銀座ルール」を策定。現在、高さ制限56mやデザイン協議会の枠組みが導入されている。2014/07/13
Ponyo
2
なじみのある銀座、確かに超高層ビルはない。場所柄、営利目的で超大型ビルがあっても良さそうなのに……ということで読んでみた。銀座の歴史から特性、そして今の銀座らしさを守るべく活動する人々のことが理解できた。なるほど、歩く楽しみ、路地の存在が銀座らしさの一つだったんだ、今更ながら気づいたり。なぜかわからないけれど魅力的。そんな銀座をこれからも守って欲しいと強く願える一冊だった。2014/04/02
Hiroki Nishizumi
1
プロローグが銀座は風俗史や文化史、個人的エッセイはたくさんあるが、建物や土地を体系的に研究したものはないという触れ込みで始まっている。なんだけれども、内容はというと合意形成が大変ですといったことが中心でそんなに面白くなかったな。2016/04/16
脳疣沼
1
そのまち独自の景観というものがあるので、いい部分を守ろうというのは素晴らしいと思うのだが、個人的には(部外者なので)超高層ビルが銀座にあっても全く問題無いと思うので、なんら感動するものがなかった。銀座ルールにより、超高層ビルは建てられなくなってしまったが、それが良いのかどうか今ひとつなところである。まちづくりは住民が能動的にマネージメントしようと思うと大変にメンドくさいということは分かった。日本中がこんなことをやっていたら、活力が失われると思うが、銀座ぐらいはこれぐらい頑固な気概があってもいいか。2014/07/07