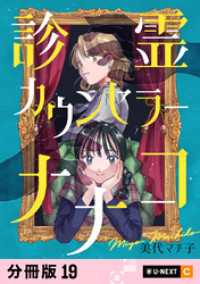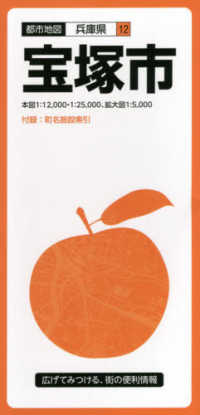出版社内容情報
9世紀アイルランドのケルト伝説から現代に至る系譜をたどり、悲恋物語「トリスタン伝説」の全貌を探る。ワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』を楽しむために必読の書!
内容説明
ワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』は、九世紀のケルト世界に起源をもつ悲恋物語。中世に宮廷詩人たちが広く語り伝えたことから、各地に無数のバリエーションが存在する。現存する断片からトリスタン伝説の全貌を描き出し、ワーグナーによる物語の独創性を探る。登場人物と楽劇の魅力を徹底的に読み解く、ワーグナー・ファン必読の書。
目次
序章 トリスタン伝説とは何か
第1章 フランスの詩人ベルールの物語体系―中世ヨーロッパの系譜1
第2章 フンラスの詩人トマの物語体系―中世ヨーロッパの系譜2
第3章 トリスタン伝説と『アーサー王物語』の結合―中世後期の発展
第4章 ワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』―十九世紀における復活
第5章 現代芸術のなかの伝説―二十世紀・二十一世紀への継承
著者等紹介
石川栄作[イシカワエイサク]
1951年高知県生まれ。徳島大学総合科学部教授。文学博士。専門はドイツ中世文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ともとも
26
物語、音楽、そして映画といった広いジャンルで 現在に至るまで語り継がれているトリスタン伝説。 いろいろな視点があって、それがかえって新鮮であったり その相違が、人間の感情がとても良く出ていて物語の面白みを誘っていく。 それでも、これもまたヨーロッパの世界観、そして、 この伝説がいかに大切に、愛されているのかというのも 感じとることが出来ました。 やっぱり伝説や神話っていいなぁ~としみじみ思ってしまう そんな1冊で良かったです。2016/01/30
かふ
16
ほとんどの人が『トリスタンとイゾルデ』というとワーグナーの楽劇を思い出すのだと思う。その成り立ちについて語っている本なのだが、面倒な人はいきなり4章から入って、ワーグナーの楽劇の内容を掴んでいた方がいいかも。それまでは、興味がない人には退屈な話かもしれない。ただ伝説だから、元の説話があり、文学になり、歌劇になったという経緯がある。そして大体重要なのはケルト起源ということだった。以下、https://note.com/aoyadokari/n/ne987541d882a2022/07/21
おくりゆう
7
各年代、場所で伝わるトリスタンとイゾルデの伝説を順に粗筋を紹介し、比較することでワーグナー作品の「トリスタンとイゾルデ」を論じる、という趣旨の本。物語自体の粗筋が読みやすく、楽しみながら、無数のバリエーションの違いを知ることができました。2013/09/09
Nyami
5
大学の授業で読んだもの。トリスタン伝説のルーツをたどり、ワーグナーの作品ではどのような独自性が見られるのか。悲哀物語である。授業では関連してワーグナーのオペラを一部みたり、2006年のケヴィン・レイノルズ監督の『トリスタンとイゾルデ』も鑑賞。この本の帯もなかなか惹きつけられるものがある。きっとオペラを最初に見てもなかなか理解できないように思う。そのルーツをたどり比較することで、ワーグナーでの表現の仕方をより楽しめるのではないか。個人的に映画では媚薬が出てこないなど、また違った視点で楽しめた。2016/02/04
たまご
4
昔オペラ「トリスタンとイゾルデ」を見たときはよくわかってなかったんですが,きちんと内容がわかると理解が全然違います・・・反省.いろいろな流布系統があって,比較してあるのも面白く.その中でワーグナーの,「愛の死」に主題をしぼってそれに向けて話をバッサリ切る味付けは,伝承とオペラの違いを感じます.アーサー王とのかかわりが今一つわかんなかったんですが,どっちの伝説が先なんだろう? 先にトリスタン伝説,あとからはやった?アーサー王伝説に組み入れられたのかな,中世騎士道の色を付けて.2013/09/29