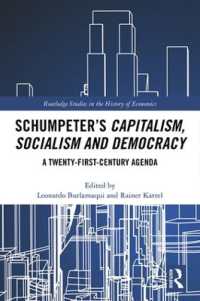内容説明
ブログやツイッター等々、傍若無人に言葉が垂れ流されている。本人は自由に自己表現をしているつもりかもしれないが、実際にそうした言葉を読むと、自由というよりも、手前勝手な思い違いとしか思えないものが少なくない。その多くは「自分探し」の強迫と享楽に憑かれている。他者の全き不在、まさにつぶやきであり、ここからは何も生まれない。「ちっぽけな自分をなくせ、他人の言葉にどっぷりつかれ!」―本書はその少々手荒な処方箋である。
目次
序章 不良中年が思想家の自伝を読みなおすきっかけ
第1章 書物という他者たちから語る(テリー・イーグルトン『ゲートキーパー』;ジョージ・スタイナー『G・スタイナー自伝』;コリン・ウィルソン『発端への旅』)
第2章 自己を語ることの策略(ルイ・アルチュセール『未来は長く続く』;ジャン=ポール・サルトル『言葉』;ミシェル・レリス『成熟の年齢』)
第3章 抵抗する自己の生(きだみのる『人生逃亡者の記録』;大杉栄『自叙伝』;林達夫『歴史の暮方』)
第4章 死ぬことを学ぶ、自己を語りはじめる(エドワード・サイード『遠い場所の記憶』;谷川雁『北がなければ日本は三角』)
著者等紹介
上野俊哉[ウエノトシヤ]
1962年生まれ。和光大学表現学部教授。冬季はカナダ、モントリオールのマッギル大学東アジア学科で客員教授を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
112
11人の思想家の自伝を、著者の読書遍歴ということで紹介してくれています。大学の講義で「自伝を読む」を行ったことがこの本のきっかけになっているようです。私には少し異なる分野の思想家が多く結構難しい感じがしました。日本人もきだみのる、大杉栄、林達夫、谷川雁の4人を取り上げていますが、せいぜい林達夫くらいが私には合っている気がします。最後に文献を紹介してくれていますがこの中から少し読もうという気になるものがありました。2015/12/06
踊る猫
33
読み返す。自伝とはその定義上人の人生のまとめを集成したものであり、別の言い方で言えば膨大な「自分語り」ということになろう。なら、この本は一見すると上野がその豊富な読書量をもとに(いい意味でも悪い意味でも「これ見よがし」「挑発的」に)書き下ろしたブックガイドのようでありつつも、その深奥にあるのは「そのようにして語らされてしまう『自分』とは何か」「そのように『語らせる』のは誰か(何か)」を問うきわめて原初的な批評意識なのだろう。ぼくもまた、こうして読書の感想を書きなぐる。だが、その「語り」は誰に貢献するのか?2024/04/28
踊る猫
24
上野俊哉の書いたものを読むといつも元気をもらっているように思う。この本も例外ではない。「反自分探し」のための書物として書かれたこの本を読むことで、上野の暴力的な(とはいえデリカシーに欠けておらず、フェミニズムも視野に入れて自己批判的に論じているところは流石と思う)、それでいて理知的なテクストに触れることで紛れもない私自身が他者と出会い、他者の言葉によって相対化されナルシシズムの呪縛から楽になるからなのだろう。そして、この本では上野自身の修行時代/青春時代の思い出も開陳される。実に親しみやすいクールな一冊だ2022/02/19
1.3manen
9
自己を語る思想家は、他人の思想を洞察して思想は打ち立てたが、自分自身をどう言説できるのか。書き出しに著者は興味をもっていることがわかる。これは、どんな文章でも第一印象が悪いと、読む気も失せるというものだから。ミシェル・レリスという人は自慰行為のことを赤裸々に描いたようだ(163頁)。思想家の人間像が解明される自伝というものは、その思想の本質はどこから生まれたか、を辿る手段ともいえる。E.サイードは白血病の治療もしていたとは知らなかった。巻末の文献案内が充実しており、読者の利便性は高い。2013/05/23
テキィ
4
わりと等身大の視点で好感2010/11/17