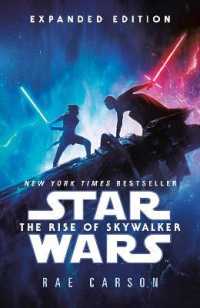内容説明
著名俳人が残した句だけが、俳句のすべてではない。俳句は、生活の中の間合いとして、その人の私的な想いを吐露する瞬間にこそ、本来的な意味を持つのである。異なる分野で活躍した6人の巨人たちの、人生の機微とはいかなるものだったのか。俳句から、まったく違う巨人の姿が見えてくる。
目次
永井荷風―薮垣の白き花
堺利彦―叩きわる厚氷
南方熊楠―妙句は語呂もじり
物外和尚―げんこつ無用
平賀源内―詩歌は屁のごとし
二世市川団十郎―あらたのしの目黒
著者等紹介
磯辺勝[イソベマサル]
1944年福島県生まれ。法政大学卒業。文学座、劇団雲に研究生として所属。その後、美術雑誌『求美』、読売新聞出版局などの編集者を経て、エッセイスト、俳人に。俳号・磯辺まさる。1992年から14年間にわたり、俳句結社誌『藍生』に投句。1999年第4回藍生賞受賞。俳誌『ににん』創刊に参加する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
S.Mori
15
俳句ではなく、他の分野で歴史に名を残した人たちの俳句が紹介されています。 一頭地を抜いているのは作家だった永井荷風の句です。「風鈴や二階からみる人の庭」のように東京の下町の情緒を今に伝える良い句を多く残しています。私は社会主義者として有名な堺利彦の句が好みでした。大らかでユーモラスな味わいがあります。逮捕されて獄中生活を送ったときに作った俳句が紹介されています「秋晴れやつくづく見入る空の色」。俳句の五七五のリズムは、日本人の感性に刻み込まれおり、俳句を詠むことが、生きることの支えになることが分かる本です。2020/03/02
志村真幸
3
著者は俳人/エッセイスト。 本書は日本史上の巨人たちの俳句をとりあげたもの。俳句を詠んでいたことはあまり知られていない人物が多く、また違った側面から眺めることができておもしろい。 出てくるのは、永井荷風、堺利彦、南方熊楠、物外和尚、平賀源内、二世市川団十郎。 あんまり上手くはなかったりもするが、その人物像がよくあらわれていたり、逆に思いもかけないような味わいのをつくっていたり。 熊楠の句に、とぼけた味わいがあっていい。 2019/04/03
Aleixo
3
始めから終りまで退屈せずに読めたのは「堺利彦」くらい。大きく取り上げられた六人よりも小波や寒村、其角の方が気になるという……。それにしても、源内のみっともないところって何だったんだろう。関心は俳句の外。2015/05/18
hitbari
1
読まなきゃ良かった。レベル高すぎてわからない。2017/05/19
デコボコ
0
永井荷風や平賀源内はともかく、南方熊楠が俳句(や都々逸)を嗜んでいたというのは驚きだったが、「この色と尼の好みや木蘭花」の読み解きなど、流石の博覧強記ぶりであった。 2013/06/20
-
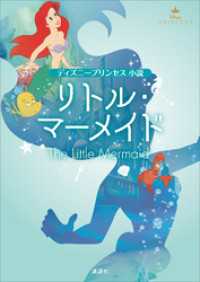
- 電子書籍
- ディズニープリンセス 小説 リトル・マ…
-

- 和書
- 長生きの本