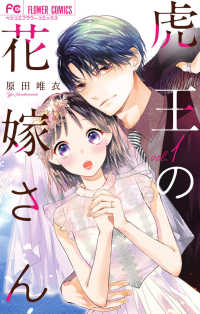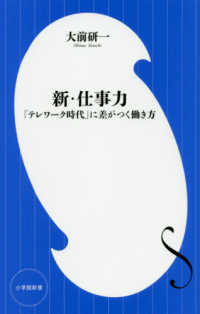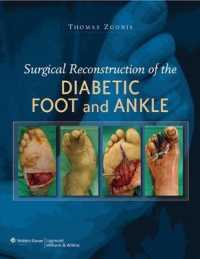内容説明
江戸中期の学者・本居宣長とはいったい誰か?昭和前期には皇国思想と結び付けられてきた歴史がある。そもそも宣長は、「日本」というアイデンティティを考察した最初の思想家だということができる。賀茂真淵との出会い、『源氏物語』と「物のあはれ」、大著『古事記伝』の執筆、上田秋成との論争、そして死。宣長の思想的発展に従って、十の問いを設定し、それに答える形で記述した宣長入門書の決定版。
目次
序 「宣長とは誰か」という問い
第1章 宣長はどう語られてきたか
第2章 宣長は自分をどう語ったか
第3章 宣長にとって真淵とはどのような師か
第4章 宣長にとって歌とは何か
第5章 「物のあはれを知る心」とは何か
第6章 宣長は『源氏物語』をどう読んだのか
第7章 宣長にとって『古事記』とは何か
第8章 宣長は『古事記』をどう読むのか
第9章 宣長は神をどう語るのか
第10章 宣長はどのように論争したか
結び 宣長にとって死とは何か
著者等紹介
子安宣邦[コヤスノブクニ]
1933年川崎市生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了(倫理学専攻)。大阪大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
35
2013.01.15(つづき)子安宣邦著。 2013.01.15 2.宣長の自伝的文章、『玉勝間』-全15巻、二の巻。 (1)「おのが物まなびものありしやう」-学問的自伝。 (2)「おのれ県居(あがたい)の大人(うし)の教(おしへ)をうけしやう」 2013/01/15
i-miya
35
2012.12.18(初著者、初読)子安宣邦著。 (序) 「大和心」とか「真心」という言葉と結びつき、『古事記』などの「日本神話」と結びつき、「物のあはれ」という美的感性と結びつく存在としての「宣長」とは誰か、と子安は問う。 第1章、どう語られてきたか。 1.宣長と「松阪の一夜」 宣長と賀茂真淵(1697-1769)との出会いの物語、劇的な出会い。 2012/12/18
i-miya
32
2012.12.24(つづき)子安宣邦著。 2012.12.24 真淵はすでに70歳近く、天下に聞こえた老大家。 宣長は、30。 真淵は、宣長の学問が尋常でないと知り、頼もしく思う。 古事記につき研究したいが、何か学問上の注意事項はありませんか。 それには、私もちょうど古事記をやりたくて、。 万葉集を調べておくことが大事だと思い、それにかかったのですが、年が年で・・・。 時間がなくて。 順序が大事です。 土台をつくり、一つ一つ。 2012/12/24
i-miya
31
2013.01.08(つづき)子安宣邦著。 2013.01.07 (ここで、本居宣長年譜) 享保五年(1730)(1歳)、松阪本町に生まれる。 元文五年(1740)(11歳)、父、小津定利、死亡。 寛延元年(1748)(19歳)、山田の今井田家に養子。 寛延三年(1750)(21歳)、今井田家を離縁、帰る。宝暦元年(1751)(22歳)、義兄死亡、家督継ぐ。宝暦二年(1752)(23歳)、遊学、京都の堀景山に入門、儒学を学ぶ。宝暦三年(1753)(24歳)、堀元原に医書を、武川幸順に医術を学ぶ。 2013/01/08
i-miya
30
2013.01.21(つづき)子安宣邦著。 2013.01.20 5.万葉集。 『古事記』注釈の業を、真淵は、宣長に託す。 私は、万葉を明らかにしたいが、年が行き過ぎている。 万葉仮名など、漢字によって表記された歌の言葉の研究を意味する。 それによって、古語の言葉遣いが明らかにされ、どのような言葉が、あるいは、どのような言葉、字音が、どのような漢字をもって表記されるかが明らかにされる。 当時の漢字音も明らかになる。 2013/01/21
-

- 和書
- マルクス派の革命論・再読