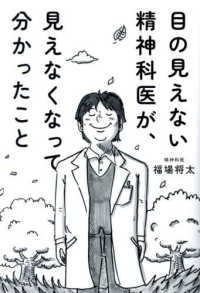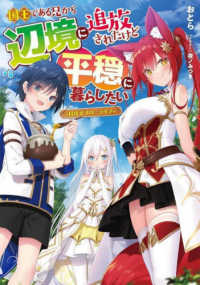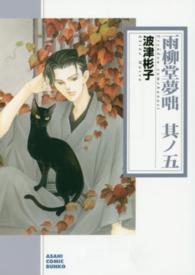内容説明
鍛冶や番匠などのいわゆる「職人」はもとより座売、振売の商賈たち、山林・海辺の生活者、遊行する聖や異形の雑芸能民、医師、陰陽師、博打、船人、そして立君、図子君…。「職人歌合」の舞台には農以外の道々の者どもが多様な姿で登場する。この異色の歌合絵巻は、いつ、だれによって、どのような動機のもとに創られたのか。和歌、判詞、画中詞を読み姿絵に注目して鮮やかに描く中世職能民の世界。
目次
第1章 「職人歌合」の魅力
第2章 「職人歌合」の成立(「職人歌合」の水源―『東北院職人歌合』;辛酉の年の歌合―『鶴岡放生会職人歌合』;維摩経と水無瀬神―『三十二番職人歌合』;『白氏文集』と代替り―『七十一番職人歌合)
第3章 「職人歌合」の世界(番いとなる「職人」たち;異色の「職人」群像;画中詞に見える「職人」たち;「職人」の土地)
第4章 「職人歌合」の文学性
諸本研究
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
8
中世以降経済の発展と共に生じた、商工遊芸等の多様だが今日では多くが失われた職業人を職人と呼ぶ。職人歌合は鎌倉及び室町期、様々な職人の諷詠に仮託し、歌合わせ形式で編纂した絵入の歌集である。今日東北院職人歌合の2種、鶴岡放生会職人歌合、三十二番職人歌合、七十一番職人歌合のみが残る。本書はそれらの分析により、成立時代、作成者、職人の多様化等や社会背景、民俗学的分析の他、掛詞を用いた滑稽味からなる狂歌の文学性にも論及し、本分野の総合的な紹介を施す。同分野では網野善彦の著作もあるが、本書の方が偏りのない良書に思える2024/10/16
-

- 電子書籍
- 転生したけどステータス「魅力」に全振り…