出版社内容情報
老熟の作家と旬の歴史家が、歴史上の人気者、西行から芭蕉にいたる平安?江戸時代をタブーを無視して縦横に斬る、異色の日本史談義。
嵐山 光三郎[アラシヤマ コウザブロウ]
著・文・その他
磯田 道史[イソダ ミチフミ]
著・文・その他
目次
その1 西行とその時代(“才能の窓”があく院政期;北面の武士の実態;ショッキングだった西行の出家 ほか)
その2 連歌の流行と俳諧の誕生(暗示と比喩―政治用語としての和歌;“言挙げしない国”;「有心」から「心の共有」へ ほか)
その3 芭蕉とその時代(大坂城の埋蔵金のゆくえ;連歌から俳諧へ;俳諧はモバイル ほか)
著者等紹介
嵐山光三郎[アラシヤマコウザブロウ]
1942年、静岡県生まれ。作家。出版社勤務を経て執筆活動に専念する。『素人庖丁記』で講談社エッセイ賞、『芭蕉の誘惑』でJTB紀行文学大賞、『悪党芭蕉』で泉鏡花文学賞・読売文学賞を受賞
磯田道史[イソダミチフミ]
1970年、岡山県生まれ。歴史家。国際日本文化研究センター准教授。慶應義塾大学大学院博士課程修了、博士(史学)。古文書などの史料を駆使して江戸時代を中心に歴史上の人物や事象に自在に迫る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
旅するランナー
61
歴史オタクなお二人のディープな対話。西行=出家した007説、芭蕉=諜報機関ボス説、和歌勅撰集=政治的求心力説が展開されます。奥の細道は、伊達家の謀反調査のためで、命を掛けた道行であり、平泉には実質2時間しか滞在しなかった事実なんて、この本でこそ、目からウロコ、魚の目に泪です。西行が死への案内人であり、釈迦の涅槃に合わせて、自ら毒を盛って死ぬ日を調節したとか、「旅をしろ。どこで死んだっていいんだよ」ってけしかけるのには、西行の、いや、最高の凄みを感じます。2019/02/19
AICHAN
40
図書館本。嵐山光三郎がこれほど歴史に造詣が深いとは意外だった。磯田道史と軽快にトークを繰り広げる。歴史の違った見方を楽しめた。2019/07/24
Syo
34
これまたタイトルに 騙されて。 って、『武士の家計簿』の 磯田さんじゃん。 それに、異才・嵐山光三郎。 西行から芭蕉へ。 なかなか読み応えあり。2018/09/13
マカロニ マカロン
22
個人の感想です:B。磯田さん嵐山さんの対談で西行、連歌師(宗祇、宗鑑、貞徳)そして芭蕉と詩歌が日本史では諜報活動に結びついていることを指摘している。芭蕉は西行への憧れを句作の中で露わにしているが、西行は芭蕉の500年も前の存在で、現代から芭蕉を見る300年よりももっと前の人と言うことになる。それを見ても西行のビッグネームぶりが感じられる。「姥桜 咲くや老後の思い 出で」、「むざんやな 甲の下の きりぎりす」が斎藤実盛を詠んだ句と知り、最近聞いた講談を思い出した2023/03/28
テイネハイランド
21
図書館本。詩歌の鑑賞に定評がある嵐山光三郎さんと、売れっ子歴史学者の磯田道史さんとの対談本です。(1)西行とその時代(2)連歌の流行と俳諧の誕生(3)芭蕉のその時代の3編で構成されています。文化的な観点からのみとりあげられてきた著名人(西行や芭蕉など)にも現実の生活があったわけで、二人の歴史好きによる忌憚のない人物談義や蘊蓄(下世話なゴシップから高尚な文明批評まで幅広い)を読めるのがこの本の売りかと思います(史実にどこまで近いかはわかりません)。このなかで西行の章は、知らないことも多く特に楽しめました。2019/01/05
-
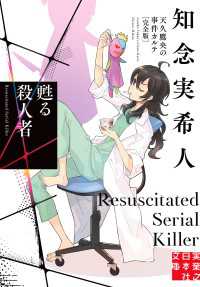
- 電子書籍
- 甦る殺人者 天久鷹央の事件カルテ 完全…
-

- DVD
- レクイエム







