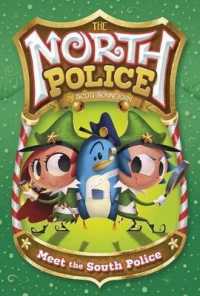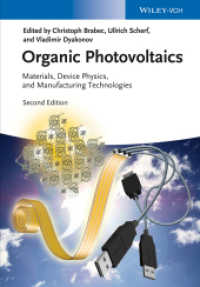内容説明
近代日本美術研究のなかで、最も問題意識に富み、生き生きした文章を書く著者による連作随筆。
目次
1 独自の美術研究―昭和十七年までの美術書(収書と散書;奥村伊九良の『瓜茄』と『神社仏閣彫刻集』;大きい本と小さい本―『画学類纂』『妙蹟図録』;『国枠』と『層雲』;山口八九子『三樹洞句録』など;三雲祥之助・高見順『百穂手翰』)
2 戦争と美術研究―昭和十八年の美術書から(近代日本美術史研究の歴史を論ず;書画家番附のこと;樋口弘『幕末明治開化期の錦絵版画』 ほか)
3 迷宮の中へ―昭和十九年の美術書から(忘れられた独自の道―木村仙秀について;木村仙秀『江戸時代商標集』;林若樹と木村仙秀;劉生と『文楽首の研究』と大小暦;日本人による最初の石版画「観光問鼎」;高橋由一の「油絵大図」など)
著者等紹介
青木茂[アオキシゲル]
1932年岐阜県生まれ。早稲田大学卒業。東京芸術大学図書館・芸術資料館、神奈川県立近代美術館、跡見学園女子大学、町田市立国際版画美術館館長を経て、文星芸術大学教授。明治美術学会会長。高橋由一研究の第一人者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
at@n
1
分野が重ならない人でも本書を読めばひいーっとなったり壁に頭を打ちつけたくなるのではないか。「誰でもがひとたび何かを調査研究しようと志したら、その日から手枷足枷金枷の蜘蛛の網にかかったと思ったがいい」のとおり蜘蛛の糸の網目が至るところにしかけられ迷宮に入り込む。著者のなかで全てが繋がっているのだが上高地の地名、明神池がわからず不明を悟った。「美は細部に宿る」とは気軽に言われるが細部とはここまで緻密なのだ。太平洋戦時下にかえって美術史研究は盛んになったという指摘は今の時代においても示唆に富んでいるだろう。2020/04/30