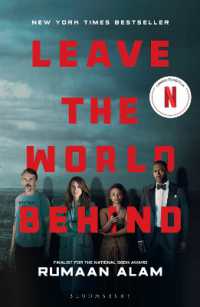内容説明
故郷福井での講演、大好評の『風の旅人』連載エッセイ、皇室についての一文、読者の質問に答える書下ろし「文字答問」等を収録。今年96歳の著者が、古今東西の資料を繙きながら綴る、豊饒なる学問世界。
目次
1(六書の説;橘曙覧の短歌史上の位置について ほか)
2(文字の世界に遊ぶ;皇室は遙かなる東洋の叡知)
3(死を超える;海―晦冥の世界 ほか)
4文字答問
著者等紹介
白川静[シラカワシズカ]
1910年、福井県福井市に生まれる。35年、立命館中学教諭となる。43年、立命館大学法文学部漢文学科卒業、同大学予科の教授となり、54年、同大学文学部教授。81年、立命館大学名誉教授。84年『字統』を刊行毎日出版文化賞特別賞受賞。91年菊池寛賞、96年度朝日賞受賞。98年文化功労者として顕彰され、99年勲二等を受く。2004年十一月、文化勲章受章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
りー
16
文字成立以前、殷王朝早期、陶器に彫り込まれた「陶文」に、既に文字の原型が存在する。そこには、ちょうど家紋にあたるような氏族の紋章も描かれている。この形がとても美しい。簡略化された形でありながら、豊かに語りかけてくる。その先にある精神世界の広がりを考えさせられる。この原型まで遡れるというのが本当にすごい。3000年以上前の思考に、現代人が触れることができ、それだけでなく、そこへの繋がりを自分の中にも感じるのだから。2020/06/27
roughfractus02
8
一般に、目を通して意味を知ることは知識とされ、身体を通して体験することは知恵とされる。私たちが本を手にして読む場合はほぼ前者であり、後者によって本を読むことは困難に思える。が、著者は本を丸ごと写すことでそんな常識を打破する。書写すると、意味を伝える道具であるはずの文字に対してなぜ、どうやってこの形になったのかという問いが生まれ、過去の人々の体験を通した知恵が「手を通じてわかる」のだという(「文字の世界に遊ぶ」)。著者が「大人」になるという時、それは身体を通じて文字に他者の経験を推し量れる段階を指すようだ。2020/12/30
hachiro86
0
万葉から明治への系譜が面白かった2009/12/13
-

- 和書
- 周縁文化と身分制