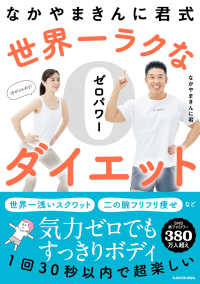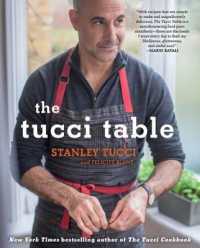出版社内容情報
かつて西洋では一年の半分を魚を食べて過ごしていた。その巨大な需要は大航海時代を誕生させ、やがて都市の興隆と自由・独立の精神をもたらす。目から鱗の魚で辿る世界史!
内容説明
十八世紀の農業革命以前、西洋の食の中心は肉ではなく魚であり、中世盛期のキリスト教社会では、一年の半分を魚を食べて過ごした。その魚への巨大な需要が、はるか遠方への航海を、漁猟と保存の技術革新を、都市の興隆を、自由と独立の精神を、ヨーロッパ近代にもたらした―。魚でたどる目からウロコの世界史。
目次
第1章 魚と信仰
第2章 フィッシュ・デイの政治経済学
第3章 ニシンとハンザ、オランダ
第4章 海と空気と同じように自由なのか?
第5章 『テンペスト』の商品ネットワーク
第6章 ニューファンドランド漁業
第7章 ニューイングランド漁業
第8章 魚はどんなふうに料理されたのか?
著者等紹介
越智敏之[オチトシユキ]
1962年、広島県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科英文学専攻修士課程修了。現在、千葉工業大学教授。専攻、シェイクスピア、アメリカ社会(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
38
新刊コーナーより。米英文学教授による食文化&欧州史です。しかもメインはお魚!まえがきから面白くて引き込まれました。海に囲まれている地域も多いしな…と考えつつ読み始めたら、冒頭がいきなりイエス・キリスト!そうそう、お魚ってイエス様のイメージでしたねえ。文学(ことわざも含め)における魚のイメージも面白いんですけど、自分はやっぱり「woman needs a man like a fish needs a bicycle」という表現が一番好きです。ロシア飛んでチョウザメ・鮭…なんて展開も少し期待しちゃいました。2024/05/25
佐倉
11
カトリックが信仰されていた旧教国では40日の四旬節や水曜日と金曜日、聖人の記念日など多くの断食日があり一年の内半分は断食日だったという。断食日中、肉は食べると熱と欲を出してしまうのでNGだが、魚は水に住んでいる粘液属性のもので穏やかな気持ちになれるため断食中も食べてもOKという四体液説に則った考え方が中世欧州にはあった。一年の半分程は魚を食べていた中世欧州民の需要を満たすため漁業が振興していくが、この時代は漁業と海軍力は密接に関わっていた。魚を中心に戦争や経済、植民地主義など多くの関係性を読み解く一冊。2024/10/30
春ドーナツ
10
なんかねえ、やたらとシェークスピアの引用(「テンペスト」にはひとつの章が与えられる)が多い。最初の断り書きで「私」は歴史家ではないけれど。とあるから、沙翁の研究者なのかと思って、巻末の著者紹介を読むのを楽しみにしていた。結果は・・・。閑話休題。というか閑話しか書いたことがないけれど。教科書的な歴史記述は退屈だけれど、ある鍵言葉を設定して、そのアングルから歴史を鳥瞰すると、いわゆるこぼれ話が満載となって、書影のようにカラフルに変身する。計測していないけれど、100回以上は「へえ」と独り言ちた。嗚呼、内容に全2024/06/28
穀雨
9
魚とユダヤ教やキリスト教の関係について論じた第一章などはすこしとっつきにくかったが、第三章以降の本論に入ると俄然おもしろくなった。副題にもある通り、北海・大西洋世界におけるニシン漁、タラ漁に焦点をあてるもので、言ってしまえば世界史のごく一部をカバーするに過ぎないが、テーマをしぼることでかえって濃密な内容になっていると思う。水でまる三日かけて戻さないといけない干し鱈がどれほどの硬さなのか気になった。2024/07/24
人生ゴルディアス
5
面白かった。中世ヨーロッパではおなじみのニシン(とタラ)の、近代にいたるまでの政治経済学。特に当時は海軍力の強さが漁民の層の厚さと相関していたから、漁業振興は海軍政策でもあった。とはいえ漁場は柵を立てて締め切るわけにもいかず、周辺国との政治から切り離されないし、そもそも水揚げした魚を売れる商品に仕立てるには技術が必要で、獲ったら必ず利益になるわけでもなかった。そして近代に入り新世界の漁場から始まるイベリア半島とイギリスを介した三角貿易にまで話が向かう。植民地政策についても詳しく語られ、盛沢山。満足。2024/04/04
-

- 電子書籍
- 天尊、都市に再臨する【タテヨミ】第40…