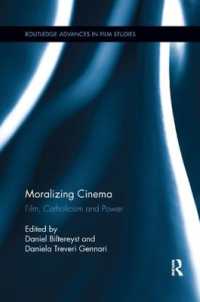出版社内容情報
エンサイクロぺディスト春山行夫が、紅茶の世界史・日本史はもちろん、アフタヌーン・ティーの心得、ティーカップの目利きまで語りつくす、面白くてためになる紅茶のすべて。解説=磯淵猛
内容説明
紅茶はいつから飲まれているのか?なぜイギリス人は紅茶好きなのか?新聞とコーヒー・紅茶の深い関係とは?海の支配者の変遷と茶、アメリカ独立と茶、植民地と茶の種類、子規とミルク・ティー…世界史・日本史に深く刻まれた紅茶の歴史から喫茶のエチケットや茶道具のウンチクまで、紅茶のすべてを平易に詳しく説き明かす。
目次
紅茶前史
十七世紀
十八世紀
十九世紀
自動販売機とティー・バッグ
紅茶の飲み方
中国茶の輸出
紅茶と陶磁器
ティー・セット
日本の紅茶
著者等紹介
春山行夫[ハルヤマユキオ]
1902年、名古屋市生まれ。『詩と評論』(1928年創刊)、『セルパン』(1931年創刊)の編集に携わるかたわら、詩人として活躍。さらに、西欧を中心とする文化史的関心にもとづき多方面にわたる著作を発表。膨大な資料の収集家としても知られる。1991年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Akito Yoshiue
8
陶磁器の話が多すぎる。2020/01/16
BATTARIA
7
紅茶について論じると、緑茶やコーヒーを度外視できないだけに、紅茶の専門家がどこまで緑茶やコーヒーについて言及するのかは、とても難しいことが伝わってくる。ニュートラルな立場でコーヒーと茶を対比して論じる本を読みたいけど、ないものねだりなんだろうな。茶とコーヒーを対等に論じるなら、酒というものを度外視できないから。この本での最大の発見は、悪評フンプンだった日本から輸出する緑茶への着色が、日持ちさせるためらしかったのと、チップの語源がTo Insure Promptenceらしいということだった。2022/08/16
minochan
5
茶摘みでは先端の若葉だけを摘むのが高級茶だというのは知っていたが、先端から順に一枚ずつ名前(フラワリングペコー、オレンジペコー、ペコー、スーチョン…)が付いているのは驚いたし興味深かった。著者の実家が戦前からの焼き物工房だった影響で、カップについても詳しく書かれている。有名なボーンチャイナの「ボーン」が本当に動物の骨を混ぜている意味だとは驚きだった。紅茶カップの方がコーヒーカップより美しく人気だ、というのはやや著者の偏見かもしれないが、共感できる。漱石にも詳しく、『文学評論』を読んでみたくなった。2025/07/22
てるてる
5
単語や当時の風俗など、調べながら読んでいたのでやたらと時間がかかってしまった。しかし、日常的に紅茶を飲んでいる者として読まないわけにはいかない。一つのテーマに基づいた世界史の本を読んだ感じでもあった。スエズ運河すごいとか、東インド会社のこととか、いろいろ学ぶことができた。毎日紅茶が飲めることに感謝しなくては。2021/07/04
あや
3
中国・日本の茶(緑茶も)が欧米に渡り各国に普及した流れや、ティーバッグの歴史、茶のカップや皿にまつわること、日本の文献に見る紅茶など、さまざまなことが多岐に渡って濃密に詰め込まれている。カップや皿のくだりでは陶磁器の歴史にまで踏み込んでいる。アッサムやセイロンについてよくわかっていなかったが少し理解が深まった。2022/03/29
-
- 洋書
- Hag Dances
-
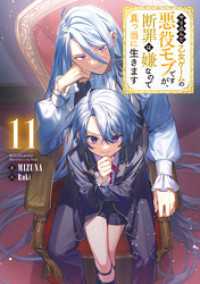
- 電子書籍
- やり込んだ乙女ゲームの悪役モブですが、…