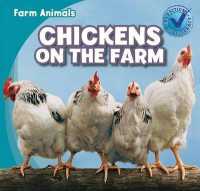内容説明
古語についての雑談をするとは、古語について「はなし」をするということ。「はなし」の原義が、肩のこらない雑談、くつろいだおしゃべりであった以上、それは、おもしろく珍しくなければならない。―この国の言葉と文学を深く広く探査した著者の学問の全身から、連想と飛躍の愉楽に満ちた百二十余の「はなし」の連環が繰り出される。
目次
はなしは庚申の晩
かなしき時は身一つ
草薙の剣
二色の虹
花ぞ昔の香ににほひける
青葉若葉の日の光
慇懃に我が思ふ君は
はや教へなん九九の算用
右は弁当、左は不便
貧窮殿
ずつなし者の節句ばたらき
雲霧といへば俳諧なり
物皆は新はるよし
大かた誤字にぞありける
文字を余す事好む人多し
よく見れば此の格なり
人さまざまよき子を持ちぬれば
祈らずとても神やまもらん
著者等紹介
佐竹昭広[サタケアキヒロ]
1927年生まれ。京都大学文学部国文学科卒業。京都大学教授、成城大学教授、国文学研究資料館館長を歴任。2008年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
しずかな午後
9
国文学者・佐竹昭広氏による古語エッセイ。もとは新聞連載のコラムで、短い話題をいろいろと見せてくれて楽しい。個人的には、抄物と万葉集の話が面白かった。抄物は、室町時代に行われた漢籍や医書などの講義録のこと。一見つまらなそうだが、現代の予備校の講義のように、色んなたとえ話や世間話が混じっていて興味深い。また、万葉集では和歌が漢字で書かれているが、その正確な読みを確定することは不可能(なものものある)と知った。だから、万葉集を読むことは、どれだけ矛盾がなく美しく読めるか、というゲームになっているのを感じる。 2022/12/18
がっちゃん
2
「不便」の対義語は「弁当」だった!?古語にまつわる小咄が充実した本書。大変勉強になりました。2013/07/18
モコトン
1
古語にまつわる小話が繋がりつつ、少し脱線しつつ連なっている。まさに、ころころと話題が移り変わる雑談という趣。古代日本には"黄色"を指す言葉が無いこと、「 匂う」の用法における嗅覚と視覚の共感覚、懈怠と懶惰の区別、万葉集の字余り歌の法則性などが印象に残った。字余りの法則を踏まえて万葉集を読むと、写本の誤字が判明して本来の歌の形が見えてくるという話からは、ただ単に読んで味わうだけで終わらせない学問の意義を感じた。懶惰を「 明日やることを今日やってしまうこと」として非難する古の価値観がとても新鮮、メモをとった。2024/01/27
A
1
>不精には2つある。「今日ノ所作ヲ明日作(ナ)スコト」を懈怠と呼び、「明日ノ所作ヲ今日作スコト」を懶惰と呼ぶ。2014/05/25
サチ
1
新聞に連載されていたコラム(?)の書籍化だけあって、一編一編が短くて濃い。タイトルを掘り下げるところから始まって、ある種しりとり的に話が進んで行くのも面白い。「色」「字余り」「誤字」絡みの話は特にオススメ。万葉集好き必読の書と言っても過言ではないかも。古今集スキーも読むべし。西行をぶった切りの宣長に笑った。沢瀉久孝氏、石垣謙二氏は凄いらしいということも分かった。とりあえず、佐竹氏・石垣氏の著作に触れてみたいし、沢瀉氏の『万葉集新釈』『万葉集注釈』を再読したい。2014/01/04
-

- 和書
- 人生を変える”神”洗顔
-

- 和書
- よくわかる酸塩基平衡