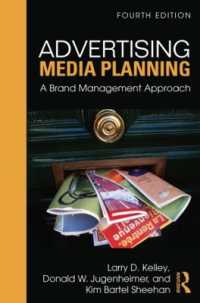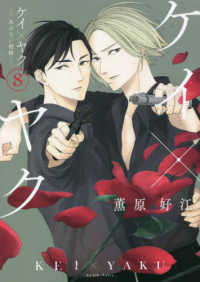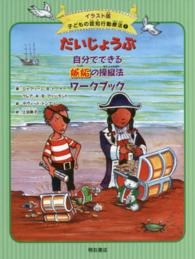内容説明
一九四五年の敗戦、いわば「滅亡体験」から、日本人は、どのように立ち上がり、どのような社会を目指したのか。廃墟や軍隊体験に関する歴史叙述を掘り起こし、さらに獅子文六、杉浦明平、花森安治、松田道雄、黒澤明らの非軍隊的・非権威主義的な「現場の哲学」ともいうべき戦後思想・文化の水脈を問い直した名著。増補決定版。
目次
第1章 廃墟から―自由について
第2章 戦後思想のなかの「軍隊」―「軍」はいかに描かれたか
第3章 『自由学校』の男と女―獅子文六の戦後
第4章 「ムラ」の政治―杉浦明平のルポルタージュ
第5章 民衆的理性のために―花森安治と「暮しの手帖」
第6章 子どもに自由を―松田道雄の仕事
第7章 戦争は終わった―私たちは何処から出発してきたのか
増補(戦後史のなかの黒澤映画;戦後少年文化のなかの乱歩)
著者等紹介
桜井哲夫[サクライテツオ]
1949年、足利市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程修了。東京経済大学コミュニケーション学部教授。近・現代社会史、現代社会論専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハチアカデミー
14
戦後、という言葉に内包される戦前との断絶を否定し、いまもなお続く戦時体制、さらにいえば日本人社会の問題点をあぶり出す。「社会の、文化の非軍事化」を目指した戦後日本は、時がたつにつれ、その初心を忘れ、形をかえた軍国主義、権威主義に堕していく。その家庭を作家や文化人の言説から明らかにする一冊である。制服やスーツ、髪型やライフスタイルまで雁字搦めにする現在は、主体性を失い、中心のないあいまいな権威に従うことを良しとする社会になっている。その根底に戦時の軍隊主義、権威主義を見いだすことは至極まっとうな指摘である。2013/06/27
Masakazu Fujino
2
93年に原版が講談社から出され、その増補版として、平凡社ライブラリーの一冊として2007年に出版された本書。戦後の原点である「日本社会の非軍事化・民主化は実現されているのか?」この著者の提起は原版出版から25年(四半世紀)経った今、ますます問い続けなければならない問題となりつつある。かつて太宰治は『如是我聞』(1948年)のなかで、民主主義の本質は「人間は人間に服従しない」「人間は人間を征服できない、つまり家来にすることが出来ない」、このことが民主主義の発祥の思想だと述べたという。私達は何をしているのか?2018/10/28