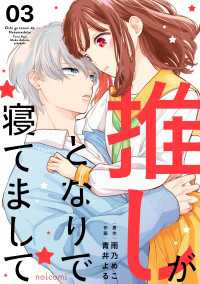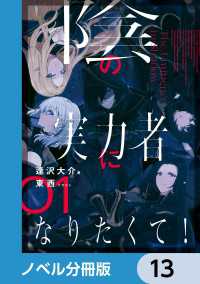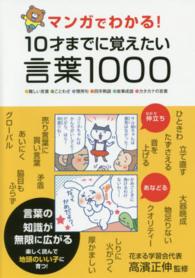内容説明
シュルツの生涯は二十世紀に翻弄されつづけた。ナチスの銃弾に斃れるその最期まで、彼が遺した小説は多くない。自身「現実の神話化」と呼んだ作品群は、特異かつグロテスク、ときに荒唐無稽に近い。だが、そこに真実がないと言えるだろうか。『肉桂色の店』『砂時計サナトリウム』の両短篇集から洩れた四篇を加えた全三十二作品を収録。元本は第五十回読売文学賞受賞。
著者等紹介
シュルツ,ブルーノ[シュルツ,ブルーノ][Schulz,Bruno]
1892‐1942。ヴィトキエヴィチ、ゴンブローヴィチと並ぶ両大戦間ポーランド・アヴァンギャルドの三銃士の一人。ドロホビチ(現ウクライナ領)に生まれる。ルヴッフ理工科大学で建築を学ぶが中退。版画集『偶像讃美の書』(1922)でマゾヒズムの美を模索した後、友人の導きで文学の世界に入る。1924~41年の間、美術教師として創作に励むが、余暇に恵まれず、残された作品は、『肉桂色の店』(33)、『砂時計サナトリウム』(37)の2短篇集と、残る4短篇の32篇にすぎない。ナチス占領下、ゲシュタポの銃弾によって白昼の路上に斃れた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コットン
66
読む人を選ぶ種類の幻想的短編集で入り込める作品とそうでないものとがあった。その中の最上のものとしては『砂時計サナトリウム』:父をある施設(病院?)に入れ見舞する主人公に起こる時間のゆらぎの中で右往左往する不思議な熱量がこちらにも伝染してきそうな作品。2019/01/23
mii22.
61
先に読んだ『アカシアは花咲く』の著者フォーゲルと親交があったシュルツに興味をもって。敬愛する皆川博子さんが最も愛する幻想作家でもあるシュルツの短篇集『肉桂色の店』のみ読了。濃密でグロテスクで繊細。何でもない日常も驚くような表現で文章化していく。ゆるく繋がった15の掌篇からなる『肉桂色の店』のうち「鳥」「あぶら虫」が強烈な印象を残す。表題にもなっている「肉桂色の店」は少年が夜の学校(ギムナジウム)の校舎にしのびこむお話。これまた大好きな長野まゆみ作品を思い出させるもので最も好みだった。2020/05/31
ドン•マルロー
32
読了後、深い感慨がこみあげた。ナチスの銃弾に倒れた著者を憐れんだわけでもなければ、才能ある芸術家の若死にに心を痛めたわけでもない。むろんその感情もないではないが、作品の内包する力に圧倒されたということの方がよっぽど大きいと言える。本書では、老人が子供化し、再び小学校に通ったり、父親が、蝿・あぶら虫・ザリガニ等に変身したりと、非現実的な現象が次々に起こる。だが、それらは、戦争の狂気やそれに感染した人間どものなす所業ほどには非現実でもグロテスクでもない。目を背けたくなるほどの非現実的な現実が、そこにはある。2016/07/13
拓也 ◆mOrYeBoQbw
28
『砂時計サナトリウム』再読。人物や街の描写中心の幻想エピファニー的な短編が多い中で、物語性が高い作品になってます。鉄道でサナトリウムに父を訪ねる主人公。父はサナトリウムの外では死んでいるが、サナトリウムには時間を巻き戻す砂時計があり、サナトリウム内の住人を生き延びさせている。ただ、シュルツ作品内の父は連作短篇の中で何度も死んでは登場し、時には別の姿にもなるので、作品単体を読む時と連作を読む時で”地平”が全く違ってくるのが特徴的です。女性に対する視線に関してもシュルツ独特の味わいを感じられると思います~2019/01/12
拓也 ◆mOrYeBoQbw
26
幻想小説集。『肉佳色の店』『砂時計サナトリウム』の二つの短篇集と、その他のシュルツ作の全小説を含む一冊です。画家としても知られるシュルツの、表現主義的な幻想小説集ですね。作風を例えるのは難しいですが、あえて言えば欧州的な梶井基次郎か、あるいは女性の性欲に怯えるカフカか、あるいはミニマムなテーマに絞ったエンデと言うべきでしょうか。時折現れる、短篇のセオリーの真逆の曖昧模糊とした掴み所の無い作品ながら、非常に面白く耽美世界を味わえる一冊だと私は思いますね(・ω・)ノシ2017/09/13