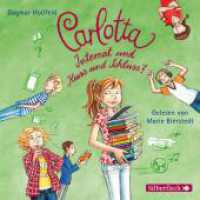内容説明
離島、マタギ・木地屋などの住みなす山間の地、「新天地」北海道など、かつて粗かった交通・通信の網の目をこぼれ落ちた地域が、列島中に散在していた。そこには、過酷な自然を相手に黙々と闘う人々の暮らしがあった。
目次
第1章 島に生きる人々
第2章 山にうずもれた世界
第3章 北辺の土地
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
31
離島、奥山、北海道の開拓地、とりあげられた場所はどこも自然条件に恵まれぬ土地。この2巻は、外からその場所に入り、猛威をふるう自然や収奪しかしない支配者とたたかい、営々と生活を築き上げた(もしくは敗れ去った)人びとの記録。◇読み進めて、「知る」ということの力、不可欠さをしみじみと感じる。土壌の構造、作物の特性、農具の使い方、そして外の世界で何が起こっているか。生き抜くためには、知らなければいけない。それは、現在も決して変わらない。生命の危機まで至ることが少ないのはそれだけ、知るハードルが下がっただけの話だ。2015/07/20
ykshzk(虎猫図案房)
22
自分は本当に上澄みの日本、しかも自分の身の回りの地域のことしか知らないと痛感。長過ぎ深過ぎとても図書館の期限内には読み終わらなかった。読むべきと言われる海外文学の長編に充てる時間をこちらに回して、日本人としてじっくり読むべきシリーズと思った。2025/05/31
シルク
15
なんか好きなんだよな〜というシリーズ第2巻。対馬の、仲睦まじかった住井夫妻の話が胸にくる。賀谷の人だったという「住井良平」という男が、下関で馴染になった女郎と離れ難くなり、自分の舟に彼女を積んだ。それがバレて賀谷では村八分にされた。「どがいな苦労しても、わしらァいっしょにおるのじゃ」(p.54)と誓って、ふたりで岩屋が浦に、乞食小屋みたいな粗末な小屋建てて、「人もうらやむほどに仲ように二人はくらしておりました」(p.54)だって。時間の彼方に名も残さずに消えていった、幸せな夫婦。なんかじんとくるんだな。2025/07/19
ndj.
12
2では対馬、十島村や青ヶ島などの島しょ部、琉球、そして九頭竜川流域や北上山地の山深い地方、さらには北海道の初期開拓などを扱う。にしても薩摩藩による琉球の黒糖独占はひどいなあ…。明治に入ってもなかなか解消されないなんて。北海道の戦災疎開移民団もひどい。だいたいひどい話しかないのだけれども群を抜いてひどい。そしてそのかげでは誰かがうまいこと、利ざやを稼いでいるのだ。この構図は古来よりかわらない。2018/03/21
CTC
11
シリーズ本編5巻中の2は「忘れられた土地」。島や山、北辺の僻地での民の生活を描く。宮本常一の著作で読んだエピソードも幾つか含まれており、1巻の衝撃ほどには“残酷”さを感じなかったというか、少々慣れがあったというか。とはいえ…「異民族であるかのようにあつかわれ、忠君愛国の志乏しきことをことごとにあげつらわれ、一種の劣等感すら抱かされていた沖縄青少年にとって、“忠良なる帝国臣民”であることを身をもってあかしする恰好の機会」として、沖縄戦を迎えた方々を想うと堪らんですね。。2021/06/03