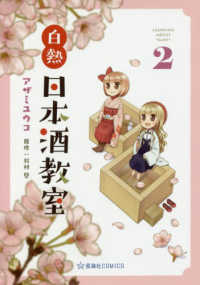内容説明
儒学や東洋学の伝統的な枠組みを超えたユニークな思想家として孔子を甦らせ、時代に先んじた孔子の洞察と着想、今を生きるわれらの「人間関係の哲学」としての『論語』を解き明かす。
目次
第1章 聖なる儀礼としての人間社会
第2章 岐路なき道
第3章 個の場
第4章 伝統主義者か予見者か
第5章 〈聖なる器〉という譬喩
解説 文化の始原から見た孔子
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
袖崎いたる
4
孔子の教え、礼と仁に注視してそこに魔術的なニュアンスをみてとる。その魔術性を根拠づけるのに言語哲学の成果に目配せし、儀礼の概念を補完していく。そう、礼とは儀礼だ。セレモニーだ。そして仁とは儀礼を意志することによって立ち上がる、その人のよさである。孔子の教えるところは行為に対しての独特な関心でもって仁の発動を見る。その関心は儀礼空間へのリスペクトであり、よきプレイヤーとしての参入意志である。著者フィンガレットによればその関心があればもうその人物は仁者なのだ。儀礼空間は術式展開や固有結界のイメージ浮かぶわい。2024/11/14
氷月
1
現代哲学の視点からの『論語』解釈。孔子は社会的な儀礼に聖なるものを見出したという。儀礼はオースティンの言語行為論のもとで行為遂行的発話として分析される。<礼>は形式主義的なものではなく、<仁>と一体であり、儀礼による相互尊重の世界が目指される。2021/11/05
oyoide
0
安冨歩・本城晴一郎 共著「ハラスメントは連鎖する」にこのフィンガレレットの論語の解釈が引用されている。 安冨氏らが示している、創発が妨げられず自己を表現でき、それで正しく他者に関わることにより「魂の植民地化」されない社会が築かれることと深いつながを感じた。 むしろ、上記本を読むことで、この本の理解に繋がる気がする。 2020/02/24