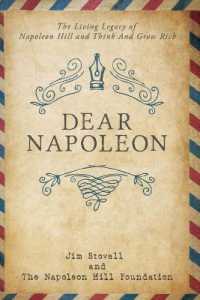内容説明
たとえば〈もの〉が仏物・僧物・人物に分かたれていたように、この時代、世界は、現代とは異質な多様な〈界〉へと仕切られていた―。一つの言葉、一片の法から中世的世界のなりたちを探りあてる。
目次
中世の「傍輩」
甲乙人
中央の儀
僧の忠節
仏物・僧物・人物
折中の法
中世の「古文書」
中世の法意識
「傍例」の亡霊
式目はやさしいか
正応元年の追加法
『結城氏新法度』の顔
「裏を封ずる」ということ
一通の文書の「歴史」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
16
「甲乙人」「中央の儀」「傍輩」など中世の裁判文書に登場するワードの考察から、中世人の法意識を探る。現代の用法からなんとなくで推察しがちな言葉の意味を、著者の「違和感」をもとに探っていく内容は、スリリングな部分が多く面白い。「神仏」と「人」、「道理」と「先例」で揺れ動く中世人の価値観は、我々の法意識や権利感覚が相対化されるような読後感も抱かせる。また平氏政権の証書の有効性を認めなかった鎌倉幕府に対し、室町幕府は北条氏も建武政権も何でもOKというのも、前政権へのスタンスの違いを表しているようで印象的であった。2021/06/27
サネキ
14
「傍輩」「中央の儀」「仏物・僧物・人物」のような言葉・概念から、中世社会に存在した、法観念、法意識を探る名著だった。笠松先生の筆致が最高で、読んでいて楽しかった。中世社会のおもしろい部分が、ここに凝縮されている。2025/04/11
あんころもち
8
中世の裁判の記録から、言葉の一つ一つに潜む人々の意識を炙り出していく。謎解きのスリルとともに、仏と人との世界を分けようとしたけど段段ごっちゃになっていく様が浮かび上がる。2016/09/05
Omata Junichi
2
時代によって言葉の意味が異なるのは当然。それでも豊富な事例に「へぇ~!」。「古き」ことは「マイナスの評価を表現」(p,141)しているという指摘からはじまる「中世の古文書」は、自分には新鮮。もうひとつ、「中世の法意識」の、御成敗式目は武士社会の「先例」や「道理」を法制化したのではない、数多の「先例」や「道理」のうち、法制定権力(北条泰時とか)が「もっとも好ましいものを選択し、それを法文化したもの」という部分(p,187~188)は、現行の日本史教科書とも異なる解釈なんですが、どうすれば良いでしょう・・・。2013/08/14
毛竹齋染垂
1
某氏に或る時「法律用語は外国語のように学べ」と言われた事が有る。 例えば『占有』や『善意』のような一見何気ない言葉も、法の世界では世間とは異なる意味を纏う。それが今昔共に変わらない現象である事を本書は示している。 しかし「昔」になると日常用語としても現代語とは乖離した意味を持つので二重の大変さが付きまとう。筆者はその言葉の周りに起きた諸現象からその言葉の持つ法的効果、更には社会的インパクトを追究する。その意味で本書は善き、言葉をきっかけとした法制史、いや歴史学への誘いである。2012/06/16