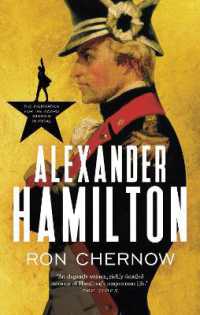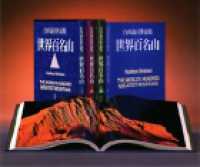内容説明
社会的地位の基準はどのようにして〈身分〉から〈富〉へと変わったのか?ファッションという日常・具体的な視点から、近代英国社会の全体像を浮き彫りにする。
目次
1 ファッションは法よりも強し―贅沢禁止法の時代
2 企業家=ジェントルマンの勃興
3 贅沢禁止法をこえて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
16
ファッションを切り口に近世イギリスの社会経済史を描いた一冊。テューダー朝で頻発された「贅沢禁止令」と18世紀の「キャラコ禁止法」を対比することで、ファッションが身分を表す贅沢品から、新たな産業の起爆剤に変化したことが示される。そしてこの旺盛な消費マインドは、来る産業革命期の爆発的な需要の予兆でもある。もちろんその裏側には原料を生産する植民地経済が隠れているのだけど、それは同著者の「世界システム論」を扱った本で補ってねというところか。『砂糖の世界史』ほどではないが、モノから歴史の広がりが見える好著である。2023/05/01
こぽぞう☆
13
ブックオフオンラインでタイトル買い。ファッションの歴史の本かと思ったら、テューダー朝から18世紀終わり頃の経済史に近い。「贅沢禁止法」の出され方が、江戸時代の幕府によるそれと重ね合わせるとなかなか興味深い。身なりで身分が分かる時代から身なりで身分を決める時代への変遷。本書が上梓されたのは1986年。「贅沢は素敵だ」なんてコピーが流行った頃?ユニクロはまだ単なる廉価屋さんで。なので、現在とは少し価値観が違う。2019/01/20
うえ
6
本来は流行と贅沢禁止法を論じた本だが、本題とは離れたスポーツ禁止法が関心を引く。1363年エドワード3世は、石投げ、鉄環投げ、ハンドボール、フットボール、闘鶏を禁じた。やがてトランプ、サイコロも禁止されチューダー朝にはテニスも標的になる(ヘンリーやチャールズ一世は好んだそうだが)。理由の一つには、スポーツを禁止し来たるべき対仏戦争に備え弓術を普及させるという「時代錯誤の発想から出たもの」だという。そして17世紀中頃、スポーツやゲームの禁止は、ピューリタン革命政権が芝居とあらゆる遊戯を禁止し、頂点を迎える。2024/08/02
ルス
4
読了しました。2025/01/04
富士さん
2
再読。スノッブな精神が商品に付加価値を与え、それが冒険心を刺激して新たな産業を興すことによって贅沢のイメージを変え、全体のレベルが上がることによって社会を平準化させていく。人文・社会科学で痛快なのは、一見無関係な要素の関係を証明して見せた瞬間だと思います。本書は珍しくない贅沢禁止法とおなじみの産業革命史を結び付け、身分が規定する贅沢から、贅沢が規定する身分への心性の移行までをも跡付けてしまうという偉業をやってのけているのです。このアイディアが降りてきたとき、著者は小躍りしたのではないでしょうか。2016/05/21