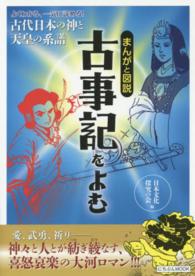内容説明
カナダの北極線上に生きるヘヤー・インディアン。厳寒のなかに生きる彼らの世界に飛び込んだ著者が綴る、フィールド・ワークの集大成。
目次
第1章 自然のなかに生きる
第2章 人生は旅である
第3章 キャンプの生活
第4章 食料を得るための労力
第5章 流動的な人間関係
第6章 人間関係の諸カテゴリー
第7章 ヘヤー・インディアンと犬
第8章 人は一人で生きるのだ―その日常性
第9章 病と死―「人と共にある」とき
第10章 ヘヤー文化とシャーマニズム
第11章 白人の世界とヘヤー・インディアン
第12章 ヘヤー・インデァンの位置づけ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
41
【始原へ14】ジェンダー研究の開拓者である故・原ひろ子20歳代の渾身の"冒険"、と言ってしまおう。当時の文化人類学の正統的なフィールドワーク(民族誌)ではある。しかし長期参与観察(だから勿論単身)を敢行したヘヤー・インディアンとは、カナダの極北の狩猟採集民族だったのだ。カナダ北極圏の中でも最北端、氷点下50度にも下る最も過酷な環境に暮らす人口500人程度の民族だ。植物は食べられないからカリブーとムースとウサギに(あと夏は魚も)頼るしかない。テントを担いでキャンプを数百キロ、獲物を求めて移動する生活だ。↓2021/03/24
C-biscuit
11
図書館で借りる。何かの本で紹介があった。忘れてしまったのは残念であり、この本を読む意味が薄れてしまった。しかしながら、結構冒険というか異文化を知るうえでも面白い。自分が生まれる前の話なので、現在がどうかは不明であるが、当時の日本人女性がフィールドワークで研究していた記録であり、ヘアーインディアンという部族の紹介である。何気ない日常なのであるが、当時の最近(?)まで、石斧などを使用していたようで、文明と接触し、鉄製の道具は画期的だったようである。また、お酒も飲んだことのない部族であったようである。興味深い。2022/03/03
の
4
アラスカ北部からグリーンランドにかけて移動しながらの狩猟採集生活を行うヘヤー・インディアンのフィールドワーク書。数十人の集団のテント仲間で住居・食事を共にし、親族であるかないかに関係無く子育てを行う。そこでは西洋近代家族の男女観は全く通用しない。さらに、氷点下三十度以下の生活では食事も毎回必要量取れるとは限らず、よって子供であろうと老人であろうと「個人で生き、責任を持つ」ことが強調される。自分とは異なった人間観の多様性を垣間見た。60年代の研究なので冷戦下での先住民族の環境の変化に触れられないのが惜しい。2010/11/14
Hiroki Nishizumi
3
とても興味深く読めた。ひとつは文化人類学としての面。人間というものはどのような環境にいても社会生活をおくる知恵は似ているものだということ。絶望しないこと、人間関係の亀裂を決定的にしないこと、など自分自身に当てはめて考えることが出来た。その一方でブッシュマンの概念など、ちょっと驚くこともあった。もうひとつは文章の書き方の面。とても読みやすく、また文章に嫌味がない。このような文章を書きたいと感じた。しかし60年代の日本人によくこのような研究が出来たと感心する。2017/10/01
みっさん
3
寒さが厳しく食料も不十分である厳しい環境下で、たくましく強く生きるヘヤー・インディアン。日本とは真逆の世界。彼らは「一人で生きている」という考えのもと、子供のころから独立した人間として扱われる。男女の性別分業や性差は最小限、社会におけるリーダーシップも最小限。「教える」「教えられる」概念がないというのは、衝撃的であった。西洋の文化流入を受けて、開発がさらに進んだ今、どういった暮らしをしているのかが気になる。2012/09/20
-

- 和書
- 諜報員狩り