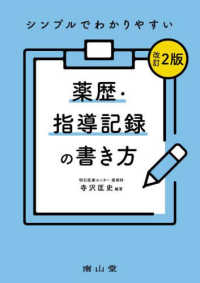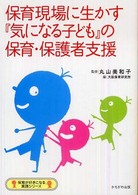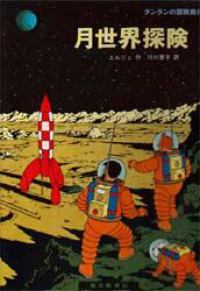内容説明
「近代の病」ナショナリズムは、克服することができるのか?グローバル化時代の難問に応える基本テキストを詳しく解析。
目次
J・G・フィヒテ『ドイツ国民に告ぐ』
J・E・ルナン『国民とは何か』
I・V・スターリン『マルクス主義と民族問題』
田辺元『「種の論理」論文集』
西田幾多郎『日本文化の問題』
F・ハーツ『歴史と政治における国民性』
H・コーン『ナショナリズムの思想』
E・H・カー『ナショナリズムとそれ以後』
丸山真男『現代政治の思想と行動』
H・アーレント『全体主義の起源』〔ほか〕
著者等紹介
大沢真幸[オオサワマサチ]
1958年長野県松本市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士号取得。千葉大学講師、助教授をへて、現在、京都大学大学院人間・環境学研究科助教授。専攻、理論社会学・比較社会学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
42
02年の本だが、もうこの規模ではこういった本はつくれないのではないか。紹介というよりは、各10ページ超にわたって各論者が力作を執筆していて、その終わりに参考文献が、巻末に索引がある。これだけ長いと各論の出来が明らかになるが、誤魔化しが効かないということだ。サイード、アンダーソン、ゲルナーが並びになっていて、編者の大澤はゲルナーを担当している。有名どころではアーレント、ファノン、ハンチントン、スピヴァク。日本人では田辺、西田、丸山、橋川文三。当時は刊行5年の加藤典洋『敗戦後論』といった変わり種がある。2023/06/02
かんがく
10
フィヒテから丸山眞男、サイード、アンダーソンなど、ナショナリズムの名著を1冊ずつ専門家が解説。ただの紹介に終わらず、内容への批判や他の本との比較なども充実している。ゲルナーの「政治的な単位と民族的(文化的)な単位とが一致すべきだという一つの政治的原理」という定義が一番しっくりきたが、やはり多義的かつ曖昧な用語であり、社会主義、宗教、リベラリズムなどとの関係の中でも捉えられる必要があると感じた。日本ナショナリズムにおいては天皇と朝鮮は無視できない。2019/11/15
ドウ
1
ナショナリズム研究における必読書50冊について、中堅の研究者がまとめた本。最初にフィヒテ『ドイツ国民に告ぐ』とルナン『国民とは何か』が置かれている以外、並んでいる順番がよく分からない。また編者の意図が前書きにて述べられているが、この意図に沿って各項目を書いているのは編者本人と佐藤成基くらいだった。とはいえ個人的には、酒井直樹やスピヴァクなど、ここで知ってから手に取った本も多いので、ナショナリズム論への入口としては(厚さがネックかもですが)良い。2016/04/29
Hisashi Tokunaga
1
FUuu- 先ずは読み終りました。「ナショナリズム」論の名著に日本の論文がこんなにたくさんとは。中堅研究者ってそこそこいるんだね。これから何に手付けるか。例えば、「地域」という概念を持ち込んでナショナリズム論とぶっつけて、スーと流れる論文がみつからなかったんだけど。つまり、今盛んに喧伝される自助・共助・公助を支えるイデオロギー、正当性は何なんだ。2013/03/30
ねぎとろ
1
論者によって多少の出来不出来はあるが、おおむね力の入った論考で、単なるアンチョコではない。もちろん手っ取り早く内容を知るにも便利。2008/12/03