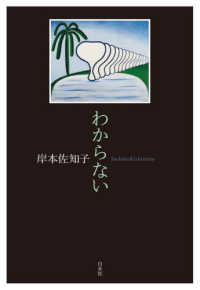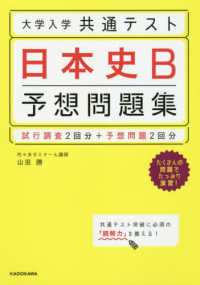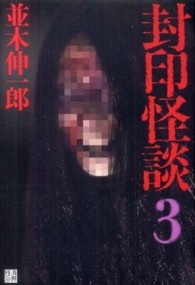- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 芸術・美術一般
- > 芸術・美術一般その他
内容説明
この人物は、本当に、源頼朝なのだろうか。絵は、頼朝の生前、十二世紀末につくられ、神護寺に納められたものとされてきた。しかし、新たな知見のまえに、数多くの疑問が湧き起こる。画風からも、描かれた風俗からも…。絵の素材についても、また、画面の異例の大きさについても…。さらに、従来、唯一の裏付け史料であった『神護寺略記』の再検証によって、画像の主を源頼朝とする通説は、根底から揺らぎはじめる。そして、この像をめぐる歴史的・社会的文脈に、虚心に眼を向けるとき、ここに、新たに一つの文書が浮かび上がる。それは、足利直義が、兄・尊氏と自らの肖像画を神護寺に納めたことを明かす願文である。世に画像は残り、人の名は忘れられる。肖像が歴史の中で果たす真の役割を問い直し、「源頼朝」像の謎を解く。
目次
1 肖像画の場―世俗人物像の場合
2 頼朝像の顔かたち、姿かたち
3 神護寺画像の名前―像主を求めて
4 頼朝像の画風と制作年代
5 「源頼朝」像は何を語りはじめるのか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kazuya
1
いわゆる「国宝神護寺三像」のうち、特に有名な「伝源頼朝像」について考察し、「足利直義像」であるとした、おそらく最初の一冊。 以前の通説への指摘だけでなく、制作当時の流行も分かるので面白い。2022/03/06
Masao Kawano
0
日本の常識=源頼朝像をくつがえした力作。久しぶりに読み返したら写真も多く、わかりやすい。特に京都等持院の足利尊氏木像、義詮木像と、神護寺肖像画の比較を見ると、実に似ている。この写真だけで、単純な僕はこの米倉氏の新説を支持したくなってしまう。歴史のミステリーとロマンを感じる歴史研究書である。2012/08/05