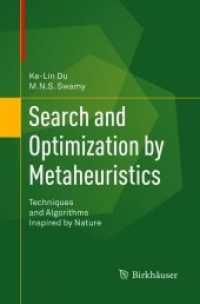目次
やきものの近代―提起されたのは何か?(先端にいる英人銅版画家;リーチの来日とその背景;リーチ・富本を結んだ楽焼;河井・浜田=陶工志望学生の登場;同年の浜田・唐九郎全く異なる土壌;リーチ・浜田=セント・アイヴスの築窯;光彩放つ河井寛次郎のスタートと苦悩;浜田の帰国と「民芸」の発足;古窯趾発掘の流行と唐九郎の活動;工人の村を理想に益子焼育つ;骨董価値と美術価値との違い;晩年のリーチと彼の遺言 ほか)
1950年以後―自己表現のための素材へ(次なる西方の使者ノグチ;彫刻の視点で作ったノグチのやきもの)
まさに、八木一夫―八木一夫オブジェ焼誕生(伝統の地に咲いた異端のやきもの;オブジェ焼とは焼もののこと;彫刻家辻晉堂・木内克のやきもの体験;アクション・ペインティングのもじりなのか;本当の陶器への思いと、技術と;自己再生の再制作・死の予感 ほか)
八木一夫、以降(加守田章二―謎の加飾の祭典;熊倉順吉―「レールなき機関車」;寺尾恍示―構成生かす「方法」の器;中村錦平―混在歓迎性と土着性と;鯉江良二―土に還る、白い器;佐藤敏―陶器に遊びの創意を;辻清明―前向きに問う古窯の摂理;三輪龍作―自伝的自己表出へ)