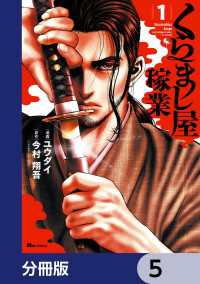目次
図解 金継ぎの方程式
1 陶器
2 磁器
3 木工品
4 ガラス
金継ぎQ&A
著者等紹介
山中俊彦[ヤマナカトシヒコ]
1947年、奈良県生れ。専門学校でグラフィックデザインを学び、都市計画などにも関わりながら、木工の仕事に入る。正倉院御物を手本にしながら、独学で木象嵌の手法を習得。素材の木はもとより、漆や金箔などの扱いに通じていることから、やがて修理の仕事も多数手がけるようになる。本漆を使っての金継ぎ講座は、現在、奈良のほかに鎌倉でも開いている。日本工芸会正会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nagatori(ちゅり)。
14
今ちょうど直したい器があったので、購入しようかどうしようか迷って、お試しに借りてきた図書館本。簡便に出来るところはして、口に触れる所等の仕上げはきっちり上質なもので、とメリハリを効かせた工程が実用的で良い感じ。購入しようかなぁ…本文とは全く関係ないが、昔愛読していた『季刊 銀花』という雑誌が2010年に休刊となっていた事を後書きで知った(;_;)ショック!2014/08/02
森
13
図書館で借りた。ザックリ読み。割れた皿があり金継ぎを試して見る予定。金継ぎ関係2冊ほど読んだが、やり方が異なる。山中方式(エポキシと漆の併用)が良さそうです。2015/03/23
Koning
12
金継ぎ自体は見よう見まねでいくつかやってきたのだけれど、この本で紹介されているのがまさかのエポキシ樹脂系接着剤も使う!という目から鱗な方法でした。その上から漆なら確かに強度も漆だけのとき以上にしっかりついて実用に耐えられる修理になる!と。ええ、今ちょうどやっとります(笑2012/07/01
ミス レイン
11
金継ぎあれこれについて、お客さんに説明しやすくなって職場でとても重宝。プロの漆屋さんの手法とはちがって素人でもできる、そして分かりやすい内容です。実際やってみると大変なんですが。買い直す方が安いかもしれない修繕費をかけてプロに頼むにしろ、道具をそろえ結構な手間をかけて自分で直すにしろ、そこまでしてでも使い続けたい直したいという突き抜けた気持ちあってのもの。時間をかけなければ進めて行けない過程がやはり「技」なのでしょう。素人でも扱いやすい「新うるし」は釣り具屋さんで入手しやすいことを付け加えておきます。2014/04/03
まげりん
7
そんな高い器じゃないが、気に入ったお茶碗がかけると凹む。金継ぎは素敵だし、自分でできたらいいなぁって思ってた。こんな簡単なのか…でも、漆が敷居高い!!ちょっと直してくれる人がいるとありがたい。私が取得すればいいのか…うーん。社会的にもっと見直されてもいい技術だと思うな。2016/11/07