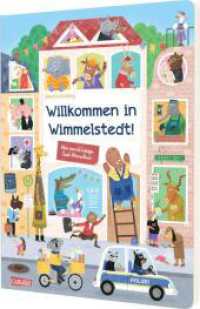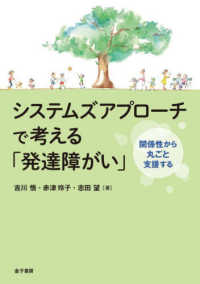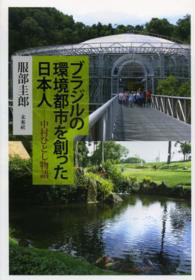内容説明
きもの美人になるために。永遠の着物バイブル。
目次
1章 きものと生きる(お洒落雑誌ができるまで;初めてデザインしたきもの ほか)
2章 きものをデザインして(私はこんなふうに着物をデザインします;今までと逆になった年齢と着物柄の関係 ほか)
3章 帯まわりのおしゃれ(帯は「細帯」になっていきます;細い帯でお洒落な着付けを ほか)
4章 きものあそび(アクセサリーとしての色半襟の美しさ;半襟の色はマフラーの粋で選びましょう ほか)
著者等紹介
宇野千代[ウノチヨ]
1897年(明治30年)山口県岩国市生まれ。岩国高等女学校卒。上京して雑誌社の事務、家庭教師、レストランの店員などをしながら文学の道を志し、24歳の時に懸賞小説『脂粉の顔』で文壇デビュー。昭和10年『色ざんげ』を発表し、翌年スタイル社を立ち上げ、ファッション雑誌「スタイル」を創刊。いったん倒産したスタイル社を、『おはん』を書いた昭和21年、新たに銀座みゆき通りに設け、のちに「宇野千代きもの研究所」を設立して雑誌「きもの読本」も同時に刊行。さらに銀座に「きものの店」を出し、小説を書くかたわら、精力的に着物のデザインを手掛ける。『おはん』で野間文芸賞、女流文学賞を受賞。95歳の時の心境を色紙にこうしたためている―「この頃 思うんですけどね 何だか 私 死なないやうな気がするんですよ はははは は」。生涯きものと関わり、平成8年、98歳で逝去
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
バニラ風味
20
宇野さんの、着物に対する思い入れは「生きている証拠」なのですね。着物の柄、帯や帯揚げなどとの相性、など、着物を普通に着ていた時代と、洋の文化が入ってきた後との考え方の違いなどが描かれています。ただ、古いことは新しく、新しいことは古いこと。流行は繰り返されるので、2004年に出版されたこの本も、「古い」とは思えません。日本の民族衣装である着物を、美しく、女性らしく装うため、宇野さんが考え、実行した工夫とアイデアは、今でも斬新に感じました。2015/11/21
Noelle
5
50年前に書かれた著者の着物に対する考え方の方が、今の呉服業界の方のお勧めのやり方より納得できる、今着物を着たい人達の気持ちに近いように感じます。高価でなくてもいい、「色合わせ」にこだわり「粋」にこだわる。今の自分が目指す方向と同じであることに とても心強い味方を得た気分です。2013/10/24
どありぶ
4
着物を普通に着てた時代の終わりの方なのかな。裄が短い着物を見て私が古着屋で買うのが短い訳がわかったり。やっぱり伊達締めは博多織りの買おうかなと思ったり。宇野さんが貧しかった頃赤い半衿を小さくさいて裏地風にするのとかステキ!2010/11/21
MIHO
3
お洒落も積極的に! 2017/02/27
波 環
3
有名女優の着物姿の写真がいっぱいなのに、なんだかへんだなーと思ったら着付けで体型補正をしてなかったり、ポーズが洋服風だったり、着丈が短かったり、裄が短かったりで違和感があるんだとだんだん気がついた。洋服風にこだわることが自己主張、これが極端すぎるように思うし、でもだからこそここの人とも思う。女性文学者きものセンス順完全わたし基準幸田文、白洲正子、群ようこ、宇野千代、中島梓、林真理子美醜じゃないんだよな。2015/06/20
-
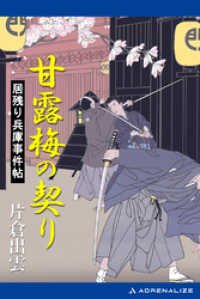
- 電子書籍
- 居残り兵庫事件帖 甘露梅の契り