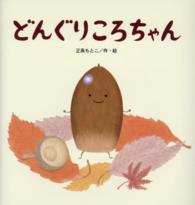出版社内容情報
「この本は、文楽観劇のド素人であった私が、いかにしてこのとんでもない芸能にはまっていったかの記録である」と著者がかたる、小説『仏果を得ず』とあわせて読みたい文楽エッセイ。文楽の真髄に迫るべく、資料を読み、落語を聞き、技芸員に突撃インタビューを敢行する。直木賞作家が人形浄瑠璃・文楽の魅力に迫る!
内容説明
あなたは、人形浄瑠璃・文楽を知っていますか?え、知らない?大丈夫、ぜったい退屈しない仕掛けが満載!ほお、ご存じですか。でもちょっと待った。あなたの知らなかったことが、こっそりと書かれています。―若き直木賞作家が、いかにして“文楽くん”に恋をし、はまっていったのか。文楽の真髄に迫るべく資料を読み、落語を聞き、突撃インタビューを敢行する愛と笑いに溢れたエッセイ。小説『仏果を得ず』と合わせて読むと、おもしろさ10倍増。
目次
鶴澤燕二郎さんに聞く
桐竹勘十郎さんに聞く
京都南座に行く
楽屋での過ごしかた
開演前にお邪魔する
『仮名手本忠臣蔵』を見る
歌舞伎を見る
落語を聞く
睡魔との戦い「いい脳波が出てますよ」
『桂川連理柵』を見る
内子座に行く
『女殺油地獄』を見る
『浄瑠璃素人講釈』を読む
豊竹咲大夫さんに聞く
襲名披露公演に行く
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
225
江戸時代に入って、秩序的なものが安定すると、芸能的な文化が花開くのでしょうかね。でも出来事を元号で言われても、ああ、あの時のかってなりませんから。でも欠かせないですね(今更感否めないけど、勉強しなきゃ)。文楽と並行して歌舞伎、落語も進歩を遂げ、題材として交流しているというのは興味深い話しですね。落語の段で桂枝雀師匠に言及があったのが、個人的には嬉しく思いました。落語家さんの噺もそんなに聴いた訳では無いですが、1番好きな落語家を問われたら朱雀師匠ですもん。2022/02/04
hiro
212
三浦しをん11冊目(エッセイ5冊目)。作者のエッセイは、読めば必ず悶絶し、電車内で読むのを控えたほうがいいものばかりだが、このエッセイは他のエッセイとは違い、「日本には文楽というこんなにすばらしい芸能があるのですよ。みなさん一度観てください」という作者の文楽くんへの愛が伝わるエッセイだった。一方、小説家三浦しをんが文楽くんに対する愛情をしをんテーストで小説にするとこのような小説になるというのが「仏果を得ず」だと思う。やはり両方読むことがお勧めだ。最後はやはり一度文楽を観に行ってみようと思った本だった。2011/10/01
射手座の天使あきちゃん
205
どう取り組んでも退屈そうな文楽と言う「秘密の花園」に鋭く突っ込む「しをん」さん 恥じらいは「むかしのはなし」、今や態度はすっかり「乙女なげやり」、結婚を望むには逆「風が強く吹いている」環境を物ともせず、読者を「悶絶スパイラル」に引き込むスゴ技に気持ちはすっかり親衛隊、でも先ずは「お友だちからお願いします」なんちゃって!(笑)2013/01/31
takaC
187
いやいや、酒気帯びのチャラ読みでも頭に入ってくるという、むしろ酔い醒ましにちょうど良いかもなしをん作品て、すごいなぁ。なんて思ったよ。2016/04/22
ユメ
168
まだ見ぬ文楽の魅力に、しをんさんにあやつられっぱなしである。古典への誘いとしてしばしば「時代が移れど変わらぬ人間の普遍的な心理を描く」といった決まり文句が用いられるが、しをんさんは「文楽には時代を経ても不変な人間の心と、時代を経ると人間の心ってけっこう変わるんだなという部分とが、そのまま刻印されている。そこがおもしろい」と言う。文楽への敷居がぐっと引き下げられたように感じた。繰り広げられる人間模様の全てを理解できなくてもいい。自分との違いも楽しめばいい。ますます文楽を観に行きたい気持ちが高まっている。→2015/05/25