内容説明
松本清張・佐野洋・都筑道夫・高木彬光に江戸川乱歩。明治から平成まで、おのれの理念をかけての筆ゲンカ。「いい大人が…」と笑うなかれ。みんな、熱いぞ。これ全部実話です。
目次
第1章 名探偵論争
第2章 匿名座談会論争
第3章 邪馬台国論争
第4章 「黒い霧」論争
第5章 「一人の芭蕉」論争
第6章 探偵小説芸術論争
第7章 本格×変格論争
第8章 ブルジョア文学論争
第9章 創成期探偵小説論争
著者等紹介
郷原宏[ゴウハラヒロシ]
1942年島根県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。詩人、文芸評論家。74年、詩集『カナンまで』でH氏賞受賞。83年、評論『詩人の妻―高村智恵子ノート』でサントリー学芸賞受賞。2006年、『松本清張事典決定版』で日本推理作家協会賞(評論部門)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぐうぐう
19
推理小説の在り方をめぐって起きた論争をまとめた『日本推理小説論争史』。甲賀三郎と木々高太郎による「探偵小説芸術論争」や、乱歩が提唱した「一人の芭蕉」論など、有名な論争もあれば、大正末期の「ブルジョア文学論争」といった初めて知る論争もあったりして、実に興味深い。時代を遡る逆編年体の構成を取ったのも効果的だ。というのも、単体で起こったかに見える様々な論争が、根っこの部分では繋がっていることが時代を遡ることでよく理解できるからだ。と言うよりも、どの論争も、結局は同じことを問題にしている。(つづく)2016/01/27
まさむね
7
「小説推理」連載時に読み、単行本でも拾い読みしていたが、改めて通して読んでみた。外野の人からすれば、細かいことなどどうでもよさそうに見えるが、当事者&ファンにとっては、時に感情的になるほど議論・論争したくなるのが、推理小説という文芸の最大の特徴であり魅力なのだと改めて感じた。乱歩vs.木々の探偵小説芸術論争から、佐野vs.都筑の名探偵論争、「このミス」匿名座談会vs.笠井潔など、有名な事件の顛末をまとめた好著。高木彬光の『邪馬台国の秘密』を巡る論争が予想外の広がりを見せてて特に面白かった。2014/09/16
かっこう
4
「一人の芭蕉」から探偵小説芸術論争にかけてが最も興味深かった。探偵(推理)小説が持つ足かせが、一般小説が目標とする高みを目指すことを邪魔するということか。最初から古くさい話が続くと読者がついてこない、という編集者アドバイスがあったそうだが、大正解。ブルジョア文学論争や創生期探偵小説論争の時代になると時代背景も文章もよくわからず、ついていけない。2021/02/23
キートン
3
推理小説に関して、過去に行われた論争とその結末についてを紹介した一冊で、後半は作者の別作品と被っていたため、前半のほうが楽しめた。 名探偵論争については、子供の頃名探偵の本を読んで推理小説というモノにハマった自分としては、都築さんの意見に一票だな。 他の方も書いているけど、容疑者Xは本格か?の論争もとりげてほしかった。 と同時に、こういう作家同士や関係者との論争は今後起こることはないのかなぁと思いながら読了。2017/07/09
Genei-John
3
名探偵論争が本格×変格論争に繋がっていることに膝をうち、更にその源流が黒岩涙香の論争にあることを知り驚嘆した。推理小説の論考らしいスリリングな論旨だと思う。2013/11/23
-
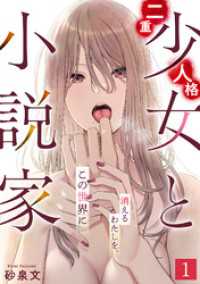
- 電子書籍
- 二重人格少女と小説家~消えるわたしを、…
-

- 電子書籍
- 史上最強婿養子【タテヨミ】第31話 p…
-

- 電子書籍
- 新しい視点から見た教職入門
-
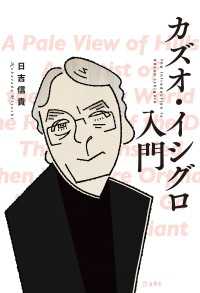
- 電子書籍
- カズオ・イシグロ入門 立東舎
-
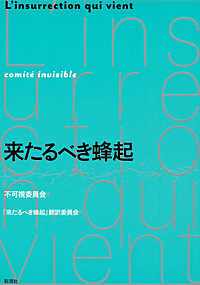
- 和書
- 来たるべき蜂起




