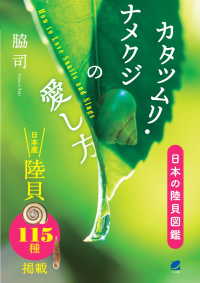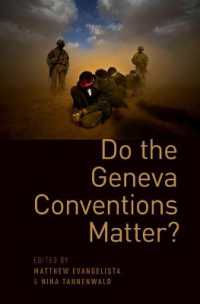内容説明
なんだか自信があるようだけど、そのプライドに根拠はあるの?有名企業に続々とゼミ生を送り込む人気教授の「大学生」&「就活」論。
目次
第1章 「大二病」の諸症状(サブカル系大二病;元受験秀才系大二病;意識高い系大二病 ほか)
第2章 大二病、就活療法編(「使える」と思われる(思わせる)ために
程々は程々に:学生時代に打ち込んだこと
学業を笑うものは学業に泣く ほか)
第3章 大二病時代の大学論(就活とスクールカースト;卒業。そしてそれから;大学は就職予備校か?)
著者等紹介
難波功士[ナンバコウジ]
1961年生まれ。専門はメディア史、広告論、文化社会学。関西学院大学社会学部教授。1984年京都大学文学部を卒業し、博報堂入社。1993年東京大学大学院社会学研究科修士課程修了。1996年、博報堂を退社し、関西学院大学社会学部専任講師に。同助教授を経て、現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
阿呆った(旧・ことうら)
14
★社会が流動化し情報が溢れ、あり得べき選択肢が多く存在する、今日のポストモダンの社会は、『自分が何者であるかということを自分自身で決めなければならない』社会です。★プライドのありかを尋ねられた時、サブカル系の大二病は「センス」、リア充系は「仲間」、元受験秀才は「テストの点数」、意識高い系は「ポジティブ」と叫びます。そのプライドをきちんと裏付ける根拠(実績)と、採用する側(相手の立場)に立つ努力が、大学生には必要だとのことです。★後半は、ひたすら就活の心構え。大学生の人におすすめかも。2016/09/07
Humbaba
8
大学生はすでにある程度出来上がった人間であるため、一人の教員が出来ることには限りがある。ゼミにおいて、場所を作ること自体は可能だが、そこから何を学び取るかについては教員よりも個々の学生に依る部分が大きい。自分から積極的に吸収していこうと考える学生はほしい物を獲得しやすいが、そうではない学生は例え実績がある場所に行っても望むような結果を得られない。2014/08/13
こっと
7
自分に過度のプライドを持ちそれを仲間同士でSNSなどを通して確認し合おうとする「大ニ病」患者への注意喚起と就活ノウハウを列挙した本。最初の3分の1ほどは「大ニ病」への強烈な批判が続き、軽い反感を覚えながらも不思議と興味が持てた。Twitterや2chなどで他人の批判ばかりしている人に(耳には痛いだろうが)是非読んでもらいたい。後半は就職ノウハウ、特に中堅私立文系の大学生を想定したかなり具体的なTipsで埋め尽くされた。正直に言うと自分には全く関係のない話だったが、就活の闇を垣間見れたような気がする。2014/09/29
Nobuko Hashimoto
7
広告業界出身らしいくだけた表現や、「就活」は実際は企業の「採用活動」なのだから有用だと思われる人間になれというところが目に付くが、そこだけをあげつらうことなく読みたい。学生に現実を直視して、しっかりと自立、自活してほしいという愛情がベースにある。その点、多いに共感する。ただ、「ふるいにかけた学生」(ゼミ生)を「出口」に導く教員の感覚だなとは感じた。「入口」(初年次教育)では、学生を「選抜」するという選択肢はないが、「ふるいにかけられても残る」学生に育てる責務はある。そこは役割やスタンスの相違を感じる。2014/08/05
かきたにたくま
6
軽快な口調で書かれる内容はなかなか面白く耳が痛い良書。高校二年生〜大学二回生くらいが読めば幻想をぶちこわして現実を受け止める準備が出来ると思う。2014/11/17
-
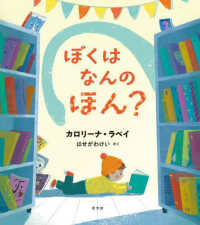
- 和書
- ぼくはなんのほん?