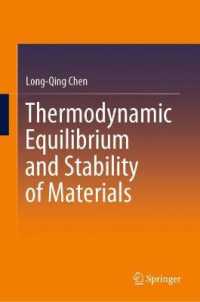出版社内容情報
インターネットで教養動画を何時間、視聴しても知識が身につかない。スマホで電子書籍を読んだが端から忘れてしまい、頭にまったく残らない。そんな経験をしたことはないだろうか。
著者は、本で得られる教養とネット・スマホの情報のあいだには隔絶たる違いがある、と語る。人間の記憶の特性上、インターネットの画面をいくら見ても教養は身につかないのだ。
また、流行のChatGPTには常識、道徳、価値観を嗅ぎ分ける力(著者いわく「校閲」)がなく、使用を誤れば社会に大混乱をもたらす、という。人工知能が危うい理由は「間違いだらけ、ウソだらけの無責任なインターネットを学習しているからです。大手出版社はどこもしっかりとした校閲部を有していて、書かれた文章の国語上の誤りばかりか、事実との相違を鵜の目鷹の目で探し、一次資料に基づき確認しています」(藤原氏)。
「ChatGPTにはこの校閲機能がありません。書物の権威、すなわち人類の知の権威は校閲に支えられている、といっても過言ではありません。これを完全に欠いたChatGPTを野放しにしておくと、やがて人類は校閲なき世界、すなわち虚実混沌の巷に落ち込んでしまいます」(同)。ネット信仰、スマホ依存から日本人を目覚めさせる一冊。
一、国語力なくして国力なし
二、読解力急落、ただ一つの理由
三、読書こそ国防である
四、町の書店がなぜ大切か
五、デジタル本は記憶に残らない
六、本を読まないアメリカのビジネスマン
七、日本は「異常な国」でよい
八、国家を瓦解させる移民依存政策
内容説明
インターネットで教養は育たない。日本人の学力崩壊、教養の低下を食い止めよ!憂国の数学者による「読書」と「書店」擁護論。
目次
1 国語力なくして国力なし
2 読解力急落、ただ一つの理由
3 読書こそ国防である
4 町の書店がなぜ大切か
5 デジタル本は記憶に残らない
6 本を読まないアメリカのビジネスマン
7 日本は「異常な国」でよい
8 国家を瓦解させる移民依存政策
著者等紹介
藤原正彦[フジワラマサヒコ]
お茶の水女子大学名誉教授・数学者。1943(昭和18)年、旧満洲・新京生まれ。東京大学理学部数学科大学院修士課程修了。理学博士(東京大学)。78年、数学者の視点から眺めた清新な留学記『若き数学者のアメリカ』で日本エッセイスト・クラブ賞を受賞、ユーモアと知性に根ざした独自の随筆スタイルを確立する。新田次郎と藤原ていの次男。著書に『名著講義』(文藝春秋読者賞受賞、文春文庫)、『孤愁 サウダーデ』(新田次郎との共著、ロドリゲス通事賞受賞、同前)、ベストセラー『国家の品格』『国家と教養』(以上、新潮新書)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MI
Aya Murakami
カブトムシ
yama1000
nami1022