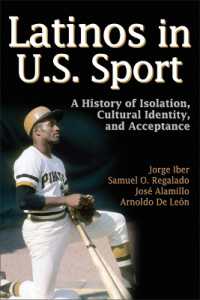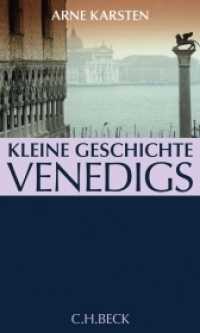出版社内容情報
「新実在論」の旗手、マルクス・ガブリエル氏は、本書の中でこう語っている。
私の存在論は、ある意味両者(編集部注:西洋哲学と東洋哲学)の統合を目指しています。
私の思想は14歳のときから東西双方の伝統に影響を受けてきました。両方が常に私の頭の中にあるのです。(中略)西洋思想と東洋思想の大きな違いは、西洋哲学が不変のものを探求している点だと思います。(中略)他方、日本人が問うのは、「変わらないものが存在するという幻想はなぜ生じるのか」です。東洋思想の立場からすると、西洋の形而上学は、初期からずっと幻想なのです。
本書は、まさにマルクス・ガブリエル氏による「西洋哲学と東洋哲学の統合」の試みの一端を示したものになったといえる。
我々(インタビュアーの大野和基氏と編集部)がガブリエル氏に、東洋哲学をテーマとしたインタビューを敢行した理由は二つある。
一つは、ガブリエル氏が東洋哲学に大きな関心を抱いていること。ガブリエル氏は、3世紀の中国の思想家王弼が著した『老子』の注釈『老子注』をかなり熱心に読み込み、老子が無常を説いていることに重要な気づきを得たという。さらに、コロナ以降たびたび来日しており、日本の思想についても高い関心を寄せている。
もう一つは、現代における東洋哲学の可能性である。現代は「入れ子構造の危機」の時代だ、とはガブリエル氏の言だが、一つの危機が別の危機に組み込まれ、拠って立つべき価値が見えづらくなっている時代において、「変わらないものが存在するという幻想はなぜ生じるのか」という問いを抱える東洋哲学の価値を、現代ドイツ哲学の第一人者が語ることには意義があるはずだ。
幸いガブリエル氏に快諾していただき、実現したインタビューは、予想以上にエキサイティングなものであった。
ガブリエル氏によると、ヒンドゥー教は「時間は幻である」と見なしている。また中国古典の『荘子』には、時空を越えた無限の宇宙に遊ぶ存在が登場する。仏教の「禅」には、座禅とは自我を消していくための訓練であるという捉え方があるが、ガブリエル氏はその志向に疑義を唱える。そして先ほど述べたように、東洋哲学は西洋の形而上学を「幻想」と見なしている。
本書の議論により、西洋哲学に関心のある方も東洋哲学に関心のある方も、上記のような哲学の主要テーマについて、従来の枠組みを超えた捉え方を得られるのではないかと期待する。巻末には武蔵野大学ウェルビーイング学部客員教授である松本紹圭氏との対談を収録。
内容説明
時間は幻か?異なる哲学の出会いが創造的思考を生む。「私の存在論は、ある意味西洋哲学と東洋哲学の統合を目指しています」と述べるマルクス・ガブリエルが、時に共鳴し、時に批判しながら、現代における東洋哲学の価値を語る。「時間は幻である」(ヒンドゥー教)、「自分は他者になれる」(中国思想)、「最上の善を求めることが人生の意味」(日本哲学)…。西洋哲学と東洋哲学の化学反応に瞠目する一冊。
目次
第1章 すべては幻想なのか(西洋哲学は不変を追求し、東洋思想はそれを幻想と見なす;西洋哲学と東洋思想は、互いに補完し合う)
第2章 仏教との対話―存在するとはどういうことか(ドイツ哲学と東洋思想の関わり;光は東方から ほか)
第3章 中国思想との対話―「無」とは何か(『老子』;『荘子』 ほか)
第4章 日本哲学との対話―西田幾多郎への批判(「純粋経験」の問題点;デカルトよりも西田が優れていた点 ほか)
巻末対談 「新実在論」と親鸞の共通点 マルクス・ガブリエル×松本紹圭(新実在論1―私たちは現実をあるがままに見ている;新実在論2―世界は存在しない ほか)
-
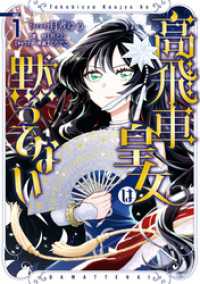
- 電子書籍
- 高飛車皇女は黙ってない: 1【電子限定…