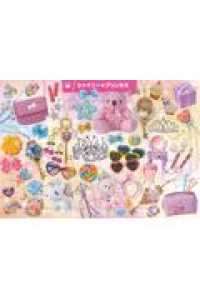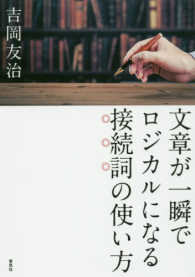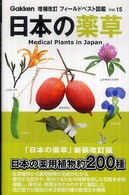出版社内容情報
ロシアのウクライナ侵攻で明らかになった自由・民主主義国家と権威主義国家の角逐、すなわち「米欧」VS「中ロ」新冷戦という構図。
しかし、「米中『対立』に基づく世界観や先進国の視線だけで、現在の世界が捉え切れるものだろうか。
第一に、非民主主義国を『権威主義体制』諸国としてまとめて理解し、民主主義国との『異質性』を強調するあまり、ロシアや中国などといった国は『合理的な選択ができない』専制主義の国と非難するにとどまり、彼らがどのような世界認識や価値に基づいて政策判断をしているのかが見えなくなる可能性があろう。
第二に、先進国とともに中国やロシアなどを主語として、開発途上国は『客体』として描かれることが多い。だが、むしろ新興国や開発途上国を主語として、なぜ彼らが時には中国なり、ロシアなりを選ぶのかという視点こそが重要なのではないか。またその際にはそれぞれの国が先進国、そして中国やロシアへの政策をいかにして決めているのかを、その内在的なコンテキスト、国内政治のありようなどから理解することが必要になるだろう」(本書「序章」より抜粋)。
「『米中冷戦』『米中競争』論では見落とされがちな、ユーラシアの広大な空間の、相互にかけ離れた固有の歴史と政治を持つ諸国家と諸勢力の主体性」(同「まえがき」)を現在、日本のアカデミズムで第一線に立つ研究者たちが明解に論じる。
内容説明
先端の研究者が「中国・権威主義体制」の行方を探る。先進国の視点では見えない世界のダイナミズム。
目次
ユーラシアへの想像力―米中対立/新冷戦の間の世界
第1部 世界を観る眼―それぞれの歴史認識とあるべき世界(琉球から見る東アジア秩序の「内在論理」;歴史認識をめぐる戦い―プーチン政権と独ソ戦の記憶 ほか)
第2部 国内政治と対外政策の因果律―それぞれの国・地域を主語に考える(南シナ海問題とマレーシア―「合理的国家」を解体する;ドゥテルテ政権のフィリピン外交―内政の論理と実利の確保 ほか)
第3部 ホット・イッシュウ―人権・科学技術・デジタル(台湾からみた人権問題の争点化;中国の科学技術力を用いた影響力の行使―宇宙分野を例に ほか)
第4部 地域問題―東アジア・アフガニスタン・イラン(中国・欧州関係の構造変化―欧州の対中警戒と対台接近はなぜ起きたか?;GCAをめぐる中国の反テロ戦略―アフガニスタンを事例として ほか)
著者等紹介
川島真[カワシマシン]
東京大学大学院総合文化研究科教授。「中国・権威主義体制に関する分科会」座長。専攻はアジア政治外交史
鈴木絢女[スズキアヤメ]
同志社大学法学部教授。専攻は東南アジア政治・政治経済・外交。著書に『“民主政治”の自由と秩序―マレーシア政治体制論の再構築』(京都大学学術出版会、大平正芳記念賞)、『はじめての東南アジア政治』(共著、有斐閣)など
小泉悠[コイズミユウ]
東京大学先端科学技術研究センター専任講師。専攻はロシアの安全保障政策。著書に『ウクライナ戦争』(ちくま新書)、『ロシア点描』(PHP研究所)、『「帝国」ロシアの地政学―「勢力圏」で読むユーラシア戦略』(東京堂出版、サントリー学芸賞)など
池内恵[イケウチサトシ]
東京大学先端科学技術研究センター教授、同センター創発戦略研究オープンラボ(ROLES)代表。専攻はイスラーム政治思想史・中東研究。著書に『イスラーム世界の論じ方』(中央公論新社、サントリー学芸賞)、『イスラーム国の衝撃』(文春新書)、『シーア派とスンニ派』(新潮選書)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ピオリーヌ
バルジ
ラピスラズリ
-
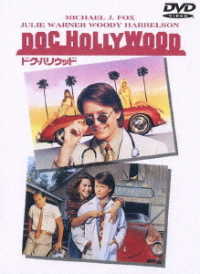
- DVD
- ドク・ハリウッド
-

- 和書
- 四季の日本・花暦12ケ月