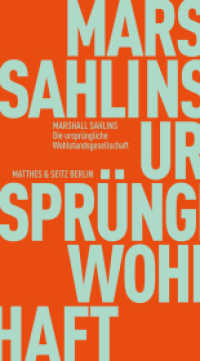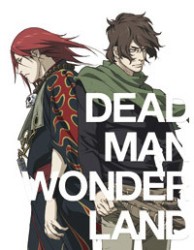出版社内容情報
子どもたちの遊び場が次々に消失し、体を使って外で遊ぶ子どもの姿を見なくなった。自殺する子どもも、後を絶たない。子どもは本来「自然」に近い存在だと論じる解剖学者が、都市化が進んだ現代の子どもを心配に思い、四人の識者と真摯に語り合う。
医療少年院で非行少年の認知能力の低さに愕然とし、子どもの認知能力の向上に努めてきた宮口幸治氏。インターネットで「正しい育児法」を追いかける親を心配する、慶應義塾大学病院の小児科医、高橋孝雄氏。国産初の超電導MRIを開発し、子どもの脳の大規模研究を行なってきた小泉英明氏。生徒が自分で野菜を育て、机や椅子も作る学校、自由学園の高橋和也氏。子どもと本気で向き合ってきた経験から紡ぎ出される教育論。
●「『ああ、そうだったの。でもあなたにも問題があるんじゃないの?』みたいなことを言ったら、一発アウトです。子どもは自分の話を否定されたことで、大人が思っている以上に傷つきます」(宮口幸治)
●「私はかねてより、『親は自分の願望を子に託すな』と訴えています。『こういう教育をしてやれば、自分にはできなかったこんな夢が実現するのではないか』というような気持ちが強すぎる」(高橋孝雄)
●「幸せのポイントは『共感』能力、言い換えれば『温かい心』(Warm-heartedness)を育むことにある、それこそ子どもたちが幸せになるための教育の最終目標であると考えています」(小泉英明)
●「結果が自分に返ってくることばかり求めていると、自分の利益になることだけをしようという発想になります。自分を超える価値や理想に触れていくことが、未来の社会をつくる生徒たちが育つうえで大切だと、私は思っています」(高橋和也)
●「何もかも手に入るわけではないけれども、生きているだけで満足できる。そんな状況を、生まれてくる子どもたちに対してつくってあげないといけないでしょう。何も難しいことではありません。親が子どもに対して『あなたたちが元気に飛び跳ねていてくれればいい』とさえ、願えばよいのです」(養老孟司)
内容説明
「子どもは本来『自然』に近い存在である」と考える解剖学者が、都市化が進んだ現代の子どもが幸せになる教育について、四人の識者と真摯に語り合う。医療少年院で非行少年の認知能力の低さに愕然とし、子どもの認知能力の向上に努めてきた宮口幸治氏。インターネットで「正しい育児法」を追いかける親を心配する、小児科医の高橋孝雄氏。国産初の超電導MRIを開発し、子どもの脳の大規模研究を行なってきた小泉英明氏。生徒が自分で野菜を育て、机や椅子も作る学校、自由学園の高橋和也氏。子どもと本気で向き合ってきた経験から紡ぎ出される教育論。
目次
第1章 「ケーキが切れない子ども」を変える教育とは(宮口幸治×養老孟司)(本当に困っている子どもは病院に来ない;ケーキを三等分できない子どもたち ほか)
第2章 日常の幸せを子どもに与えよ(高橋孝雄×養老孟司)(違和感にいち早く気づくことが仕事;親には、本能的に「子どもの心を読み取る力」が備わっている ほか)
第3章 子どもの脳についてわかったこと(小泉英明×養老孟司)(まことしやかな「神経神話」;子どものころから「測る」ことが好き ほか)
第4章 自分の頭で考える人を育てる―自由学園の教育(高橋和也×養老孟司)(自由学園での講演で話したこと;外面的な成功ではなく、人間としての成長を願う学園 ほか)
著者等紹介
養老孟司[ヨウロウタケシ]
1937年、鎌倉市生まれ。東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。95年、東京大学医学部教授を退官し、同大学名誉教授に。89年、『からだの見方』(筑摩書房)でサントリー学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
きみたけ
南北
けんとまん1007
とよぽん