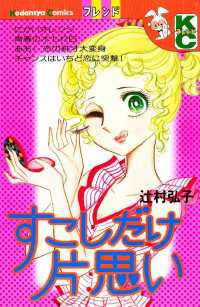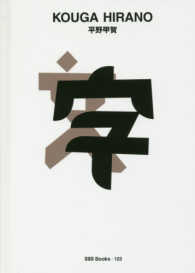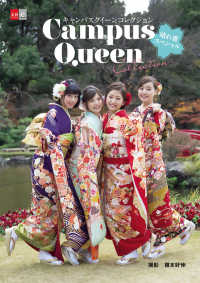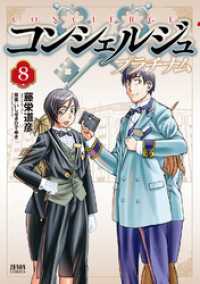- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
出版社内容情報
日本人が日常生活で何気なく使っている言葉、当たり前のようにしている行動の古来からの意味を掘り下げて解説する。
内容説明
別れのことばは、なぜ「さようなら」なのか?なぜ、白い色の自動車を好むのか?考えてみれば不思議な日本人の言動や習慣には、驚きの歴史があった!―。
目次
投身自殺でなぜ靴を脱ぐのか?
失恋するとなぜ北に向かうのか?
なぜ座席の端に座りたがるのか?
エスカレーターではなぜ右、左に立つのか?
歌謡曲にはなぜ雨がよく降るのか?
新興住宅地にはなぜ「丘」という地名が多いのか?
五月に鯉のぼりを揚げるのはなぜ?
上野公園にはなぜ西郷さんの銅像が建っているのか?
「おかげさまで」となぜ言うのか?
食事のはじめになぜ「いただきます」と言うのか?〔ほか〕
著者等紹介
大森亮尚[オオモリアキヒサ]
1947年、神戸市生まれ。上智大学大学院博士課程修了。大学院の頃より民俗採集調査に全国を歩き回る。専攻は日本民俗学をベースにした上代文学・芸能史の研究。霊魂信仰研究や怨霊研究を通じて日本人とは何かを問い続けている。武庫川女子大学、兵庫大学教授などを経て、現在、古代民俗研究所代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
11
はしがきの驚愕の事実は、著者が3.11の前日に、津波の恐怖を講義していたということであった。大預言者たる威風すら感じさせた。そんなことってあるのだな、と。何か、第六感が働く民俗学の奇妙なところか。色々な素朴な問いを設け、解説していくスタイルから成り立っている。「第七話 五月に鯉のぼりを揚げるのはなぜ?」に注目した。あれは何の旗ですか? と外国人が尋ねたら、と。うーむ。魚を揚げる理由までは・・・、と。持統天皇の田植え、出世の象徴の鯉。黄河の龍門を上る鯉。江戸以来のこと。古代は女子の早乙女を祝っていたという。2013/05/26
たかみ
1
【図書館】日本人ってなんだろうと、ふと疑問に思った時に見つけた本2014/11/27
まゆまゆ
1
なぜ右が神聖で左が不吉なのか、なぜ食べる前にいただきますと言うのか、など当たり前に使ってる日本語も、一度なぜ?と突き詰めていくと、意外な点に辿り着ける、と。柳田国男恐るべし!2013/03/07
unya
1
思いあたる節がありすぎました(笑)2012/12/22