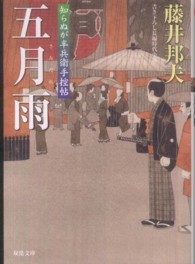出版社内容情報
耕さない田んぼ、「家族と食」に関する本物の社会調査……。養老孟司が自身を驚かせた4人と共に、日本人の基本的な問題を問い直す。
【著者紹介】
解剖学者
内容説明
日本人の「家族の絆」の実態を調査し続ける岩村暢子氏。耕さず農薬も肥料も使わない農業で強い米を作った岩澤信夫氏。植林活動で海を変え、震災も淡々と受け止める牡蛎養殖家畠山重篤氏。日本になかった合理的な間伐を普及する鋸谷茂氏。ごくふつうの日常を研究する人、リアルな「モノ」に携わる人と解剖学者が、本当に大事な問題を論じ合う。「日常から消えた『現実』」「不耕起栽培で肥料危機に勝つ」「ダムは造ったふりでいい」「人工林を救う管理法」…地に足をつけて考える一冊。
目次
第1章 現代人の日常には、現実がない―養老孟司×岩村暢子(進む食の「個化」;「ご馳走」の意味合いが変わった ほか)
第2章 田んぼには肥料も農薬もいらない―養老孟司×岩澤信夫(田んぼを耕さないコメ栽培;天啓を受けて ほか)
第3章 山と川に手を入れれば、漁業は復活する―養老孟司×畠山重篤(海は生きていた;赤い海を青く ほか)
第4章 「林学がない国」の森林を救う―養老孟司×鋸谷茂(川と森がつくってきた歴史;山から材木をどう運ぶか ほか)
著者等紹介
養老孟司[ヨウロウタケシ]
1937年、鎌倉市生まれ。東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。95年、東京大学医学部教授を退官し、同大学名誉教授に。89年、『からだの見方』(筑摩書房)でサントリー学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ニッポニア
こも 旧柏バカ一代
柊
1.3manen
Humbaba
-
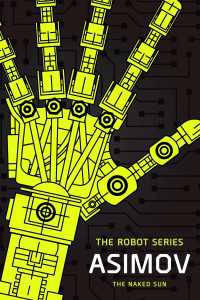
- 洋書電子書籍
- The Naked Sun
-
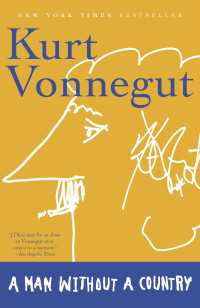
- 洋書電子書籍
- カート・ヴォネガット『国のない男』(原…