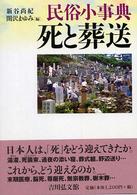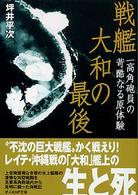- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > 学習
- > 文明・文化・歴史・宗教
出版社内容情報
「ようおこしやす」おもてで商売をして、奥で生活をするのが町家です。カフェ桜を営む福ねこさんとお豆さんが、町家を案内してくれます。
【著者紹介】
イラストレーター、京町家友の会、四条京町家会員
内容説明
ようおこしやす。おもてで商い、奥で生活をする和の住まい、京町家。「カフェ桜」の福ねこさんとお豆さんが、ご案内します。
著者等紹介
山口珠瑛[ヤマグチタマエ]
京都生まれ。京都教育大学特修美術科西洋画卒業。イラストレーター。アトリエTAM主宰。京町家友の会、四条京町家会員
松井薫[マツイカオル]
1950年京都生まれ。大阪工業大学建築学科卒業後、ゼネコン現場監督、大手不動産系リフォーム会社を経て、1998年一級建築士事務所「住まいの工房」を設立。個人住宅を中心に、特に中間領域と呼ばれる、内でも外でもない部分のエネルギーのやり取りに着目して、設計活動中。京町家の保全再生活動にも関わっている。一級建築士。京町家再生研究会理事、京町家情報センター代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
35
京都の独特な雰囲気を楽しめる絵本です。町屋に昔友人が住んでいて、色々作りを説明してもらっていたのですが、かなりリノベーションされていたので建具は現代的だったのよね…次回京都に行くときはぜひ伝統的な建具を拝見したいです。面白かった!2022/05/25
Y2K☮
34
手元に置いておきたい一冊。空間を緩やかに区切る日本家屋の美点と機能性に不思議な癒しを感じる。そこはかとなく意味が漂いつつ、必要以上に堅苦しくない風の中で住人も客人も羽を伸ばして寛げる。面白い小説も或いはこういうものではなかろうか。豆腐屋の格子は水が外へ跳ねないように腰まで板張りだが、呉服屋は反物の色の違いが見えるように縦の桟を数本ごとに短くして光を多く室内に取り入れる。米屋のは防犯の為に頑丈。炭屋だと炭の粉が飛び散らないように格子の幅が小さい。長い物を収納できる箱階段もいいアイディア。楽しく学べました。2015/06/19
Naomi
34
「町家」がどういうものなのか、だいたいわかった。絵がかわいくて、わかりやすい。町家は本当によくできているなぁと思った。おもての顔とも言える格子は、デザインによって商売がわかるようになっているのが、おもしろかった。それぞれ、しっかり機能的でもある。この絵本、読めてよかった。2014/08/07
Gummo
32
昔ながらの京町家でカフェを営む福ねこさんとお豆さんが町家の中をご案内。職住一体の空間である町家の造りがよく分かる。暮らしを快適にする知恵・工夫や、商売による格子の違いなど、大人でも勉強になる絵本。★★★★☆2015/04/26
る*る*る
31
お気に入り本♡図書室蔵書にはまだしていない。調べ学習で、これをテーマにする子どもがいたら即(^_−)−☆ それまでは、時々図書館で借りて妄想しまくります♡えびす小路の他の住人たちの店屋を是非とも続編として出して〜!2015/11/16