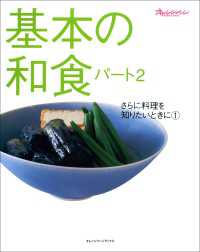出版社内容情報
物価とともに雇用や消費が下がるデフレは、まだ続く。「290円弁当」に見る経済格差など、身近な現象から新時代の常識を読み解く。
「高齢化社会では富裕層がターゲット」、「これからのマーケットは中国市場」、「ヘッジファンドの投機が市場を破壊する」、「米国流の金融覇権主義と市場原理主義はいまや崩壊した」……。新聞や雑誌の語るもっともらしい理屈が、私たちの社会生活に浸透している。だが、「マスコミが画一的に報じる経済問題の『常識』は、本当に正しいのか。じつは、それは合理的に考えてみると『非常識』ではないのだろうか。さまざまなテーマについて、身近な経済指標やエピソードを交えながら、わかりやすく解説するよう心がけたつもりである。サラリーマンや経営者層のみならず、主婦や学生など、幅広い方に読んでいただければ、と願っている」(本書「はじめに」より)。本書を読み解くキーワードは「デフレ」。人口減少で「お金を使う人」の数が減少するなか、どうすれば企業の利益と賃金は上がるのか。6年連続人気ランキング1位のエコノミストが記す、真摯な考察の書。
●はじめに
●第1章 「米国の金融覇権」は続く
●第2章 高級車ブームにご用心
●第3章 地銀の危機と道州制
●第4章 ミステリーのなかの大恐慌
●第5章 数字で読む「クルマ離れ」
●第6章 教壇廃止が社員を弱くする
●第7章 なぜ円だけが乱降下するのか
●第8章 ここまで深刻「食のデフレ」
●第9章 個人消費を伸ばす「滞在人口増加策」
●第10章 投機は市場の「必要悪」
●第11章 「サイボーグ経済」崩壊の始まり
●第12章 “ドル”は中国の不良債権
●第13章 「不均衡是正論」の本当の狙い
●第14章 オーストラリア絶好調の理由
●第15章 消費にかかる「時間」というコスト
●第16章 「バブル崩壊」は予防できるか
●第17章 金融政策はアートかサイエンスか
●第18章 黒子役に徹し、活気づく銀行
●おわりに
内容説明
値下がりする食品・衣料、上がらない給料。なぜ円だけが乱高下するのか?2010年を生きるための「常識」。
目次
「米国の金融覇権」は続く
高級車ブームにご用心
地銀の危機と道州制
ミステリーのなかの大恐慌
数字で読む「クルマ離れ」
教壇廃止が社員を弱くする
なぜ円だけが乱高下するか
ここまで深刻「食のデフレ」
個人消費を伸ばす「滞在人口増加策」
投機は市場の「必要悪」
「サイボーグ経済」崩壊の始まり
“ドル”は中国の不良債権
「不均衡是正論」の本当の狙い
オーストラリア絶好調の理由
消費にかかる「時間」というコスト
「バブル崩壊」は予防できるか
金融政策はアートかサイエンスか
黒子役に徹し、活気づく銀行
著者等紹介
上野泰也[ウエノヤスナリ]
みずほ証券チーフマーケットエコノミスト。1963年、青森県生まれ。出身は東京都国立市で、両親の実家は秋田県。85年、上智大学文学部史学科(西洋現代史専攻)卒業・法学部法律学科学士入学。86年、会計検査院入庁。88年、富士銀行(現みずほ銀行)入行。為替ディーラーを経て、90年から為替・資金・債券の各セクションでマーケットエコノミストを務める。2000年、みずほ証券設立に伴い、現職に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マイン
rebanira_itame_man
muko1610
Humbaba
マープル