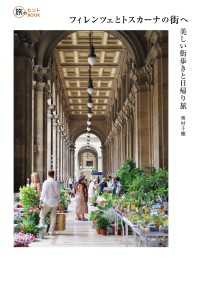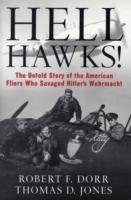出版社内容情報
生前の三島自身から高く評価を受けていた著者の三島に対する過去の論考をもとにして新たに綴る。三島がこの世を去った日を目前に刊行。
1970年11月25日――日本人が忘れてはならない事件があった。生前の三島由紀夫から「新しい日本人の代表」と評された著者が三島事件に関する当時の貴重な論考・記録・証言をもとに綴る渾身の力作。日本が経済の高度成長を謳歌していたかにみえる1970年代前後に、文壇で確固たる地位を得ていた三島の内部に起こった文学と政治、芸術と実行の相剋のドラマを当時いわば内側から見ていた批評家こそが著者であった。その著者が、戦後の文芸批評の世界で、小林秀雄が戦前に暗示し戦後に中村光夫、福田恆存ほかが展開し、三島由紀夫も自らにもちいた「芸術と実行」という概念のゆくえについて、40年近くもの時を経て、著者としての答を出すことを本書で試みた。また、著者は「三島の言う『文化防衛』は西洋に対する日本の防衛である。その中心にあるのは天皇の問題である」として、三島の自決についても当時の論考や証言を引用しつつその問題の核心に迫る。
●はじめに ――これまで三島論をなぜまとめなかったのか
●第一章 三島事件の時代背景
●第二章 一九七〇年前後の証言から
●第三章 芸術と実生活の問題
●第四章 私小説的風土克服という流れの中で再考する
●〈付録〉不自由への情熱 ――三島文学の孤独(再録)
内容説明
1970年11月25日―日本人が忘れてはならない事件があった。三島由紀夫から「新らしい日本人の代表」と評された著者が三島事件に関する当時の貴重な論考・記録・証言をもとに綴る渾身の力作。
目次
第1章 三島事件の時代背景(日本を一変させた経済の高度成長;日本国内の見えざる「ベルリンの壁」 ほか)
第2章 一九七〇年前後の証言から(日本という枠を超えるもう一つのもの;三島由紀夫の天皇 ほか)
第3章 芸術と実生活の問題(本書の目的を再説する;芸術と実行の二元論 ほか)
第4章 私小説的風土克服という流れの中で再考する(小林秀雄「文学者の思想と実生活」より;明治大正の文壇小説と戦後の近代批評 ほか)
著者等紹介
西尾幹二[ニシオカンジ]
1935年東京生まれ。東京大学文学部独文科卒業。同大学大学院文学修士。文学博士。ドイツ文学者として、ニーチェ、ショーペンハウアーの研究、翻訳を出発点とし、その後、文学、教育、政治、国際問題など幅広いテーマをめぐる評論活動を精力的に展開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。