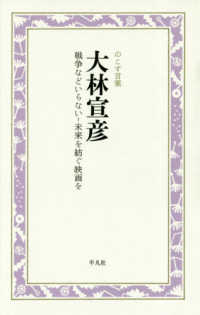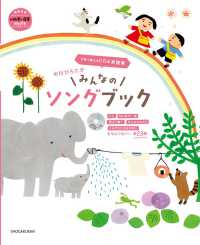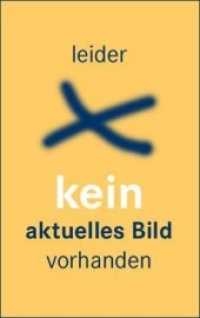出版社内容情報
叱らずに「いい習慣」が身につく! この本には、叱らなくても、子どもが自然に「いいこと」ができるようになる具体的方法が満載です。
叱らずに、子どもに「いい習慣」をつける方法。
しつけや子育ての本はたくさん出版されています。でも、そのほとんどは心構えを述べたものであり、親が一番知りたい「どうしたら実際にそれができるようになるのか?」の具体的な方法を書いたものは、極めて少ないといえます。
▼そこで本書で著者は、たとえば次のことができるようになる具体的方法を提示しています。「自分で片づける」「忘れ物をしない」「やる気をもって取り組む」「自分で勉強を始める」「早寝早起きをする」「ゲームのやり過ぎやテレビの見過ぎを防ぐ」「危険から身を守る」「進んで歯を磨く」等々です。
▼また、「しつけとは、注意したり叱ることである」と大きな勘違いをしている親が非常に多いといいます。この本では、合理的な工夫をすることによって、叱らなくても子どもが自然に「いいこと」ができるようになる環境とシステム作りを提案しています。
▼実生活ですぐに役立つ具体例がふんだんに盛り込まれた、まさに親にとって待望の本といえよう。
●第一章 子どもの「いい習慣」は親の工夫から
●第二章 このアイデアが子どもを伸ばす
●第三章 叱らなくても自然にできる環境とシステム
内容説明
「自分で片づける」「忘れ物をしない」「やる気をもって取り組む」など、叱らなくても子どもが自然に「いいこと」ができるようになる具体的な方法を紹介しています。
目次
第1章 子どもの「いい習慣」は親の工夫から(特効薬「一日一〇分の片づけタイム」で「片づけができない」悩みは一発解決!;物の置き場所に「おもちゃ」「学校用品」などの明示をするだけで、片づけ力がアップする;親が簡単収納の環境とシステムを作ってやれば、片づけ時間は半分になる ほか)
第2章 このアイデアが子どもを伸ばす(悩みの種の「ゲーム遊び」については、ルールを決める;ルールを決めたら、紙に書いて明文化し、親子で誓いのサインをして目立つところに貼る;にんじん方式、サンドイッチ方式など、複数の選択肢の中から子ども自身に選ばせると遵守意識が高まる ほか)
第3章 叱らなくても自然にできる環境とシステム(叱ることには二つの大きなマイナスがある;「イライラして叱ってしまう」のには、三つの理由がある;合理的な工夫「叱らなくても自然にできる環境とシステム」 ほか)
著者等紹介
親野智可等[オヤノチカラ]
1958年、静岡県生まれ。本名・杉山桂一。公立小学校で23年間教師を務める。教育現場の最前線に立つ中で、親が子どもに与える影響力の大きさを通感。教師としての経験・知識・理解・技術を少しでも子育てに役立ててもらいたいと、2003年に無料メールマガジン「親力で決まる子供の将来」の発行を開始。具体的ですぐできるアイディアが多いとたちまち評判を呼び、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど各メディアで絶賛される。また、子育て中の親たちの圧倒的な支持を得て、まぐまぐメルマガ大賞の教育・研究部門で04~07年の4年連続第1位に輝く。読者数も4万5千人(08年9月現在)を超え、教育系メールマガジンとして最大規模を誇る。2006年3月に退職後は、講演や執筆に精力的に取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mug
しぃ
あべし
やもち
AI