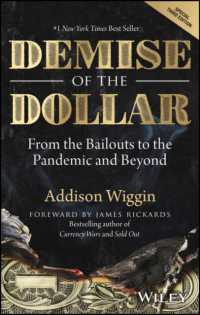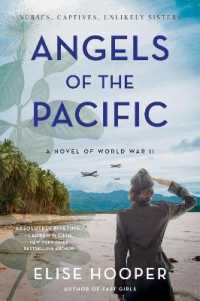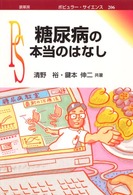内容説明
京都・島原といえば、かつて興隆をきわめた、日本でいちばん古い廓。その地でたった一軒、現在でも営業を続けるお茶屋が輪違屋である。芸・教養・容姿のすべてにおいて極上の妓女、太夫を抱え、脈々と三百年の伝統を受け継いでいる。本書では、輪違屋十代目当主が、幼き日々の思い出、太夫の歴史と文化、お座敷の話、跡継ぎとしての日常と想いを、京ことばを交えてつづる。あでやかでみやびな粋の世界―これまでは語られなかった古都の姿が、ここにある。
目次
第1話 輪違屋に生まれて―跡取り息子の日々
第2話 最古の花街島原、最後の置屋輪違屋
第3話 極上の妓女・太夫
第4話 京都の花街
第5話 お座敷にあそぶ
第6話 きょうの輪違屋十代目―廓の情緒
著者等紹介
高橋利樹[タカハシトシキ]
1948年、京都生まれ。輪違屋十代目当主。1971年、大学卒業と同時に当主を継ぐ。日本最古の廓、京都・島原に現存する置屋兼揚屋であり、創業三百余年の歴史を誇る、輪違屋の伝統を担う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mimi
9
『輪違屋糸里』下巻の対談にも登場していた輪違屋の十代目ご当主の著書。輪違屋さんに実際足を運んだ上で読んだのでとても感慨深かった。ご当主の幼少時以来の経験や、過去の名だたる太夫たちや江戸吉原との比較、京の五花街の紹介、お座敷遊びの作法に至るまでがやさしい語り口調で綴られている。時代が変わる中、伝統を守り伝えていくことの難しさ、そして輪違屋さんが確かに現在もお茶屋さんとして太夫さんを抱えて営業されているのだということが実感できた。2014/08/31
ミナ
7
この間『この世をば』を読んで生きる世界の違いを感じたものだけど、これまた違う世界。芸の道を極めた太夫さんは御所にあがれて貴族たちを相手に遊び満足させる。それだけ雅で教養を求められる。そりゃ、新選組とかこんなことができる身分になったかーと悦には入れど、教養はたりないせいで面白さは十分に感じられず、酒のんで暴れて嫌われるのね。納得した。輪違屋さんももしかしたら最後かもとのこと。このような文化が失われるのは悲しいけれど、維持するには時代が変わりすぎたのだろうか…。2024/08/07
Moeko Matsuda
6
一見さんお断りの幽玄の世界…。実は著者である輪違屋のご当主に一度直接お会いしたことがあって、その人柄の思いがけないざっくばらんさにすっかり大好きになってしまったワタクシ。ものの数時間で読み終えてしまったこの本には、いろんな情報が詰まっている。華やかさと裏腹の切なさ、素人には踏み込めない独特の倫理観や世界観。変わっていく時代の中で、変わらないことの難しさを感じさせられる、ご当主のお人柄そのままに、「飾らない」調子で島原のホントのところを教えてくれる一冊です。歴史好きにもオススメします!2018/01/29
min
5
夏の特別拝観で輪違屋に行ったのをきっかけに読んだ。知らない世界ってまだまだあるんだな。不景気になり旦那さんもつかないご時世に続けて行くのは大変だと思う。また太夫さんを目指す人の意識も変わっているから尚更だ。でも出来るだけこのような世界を守っていってほしいと願う。2014/08/19
isao_key
5
京都島原で元禄時代から続くお茶屋「輪違屋」の10代目当主が花街の歴史、歴代の太夫たち、お座敷での作法など、一生縁のないだろう世界について細かく教えてくれる。まず太夫とは最上位の遊女のことで、各種芸能でトップのみに与えられる称号をいう。安政3(1774)年の調べでは京都島原傾城で549人中、太夫は3%しかいなかった。太夫の下には天神、白人、半夜、鹿恋と序列があった。これはまさに横綱になるのに等しい。また太夫の名は源氏物語の帖の名や人名からつけることが通例となっていて、ここから源氏名と言われるようになった。2014/07/27