出版社内容情報
日本の食料自給率について考えてみよう!
日本の食料自給率は、先進国の中でも最も低い40%。穀物、野菜、肉、魚など、さまざまな食べ物の自給率と今後の課題を徹底解説!
「食」に対する関心が高まる現在、日本の食料自給率の低下が大きな問題になっている。1960年には80パーセントあった食糧自給率が、今では40パーセントと、大きく低下している。さらに、先進国の中でも自給率40パーセントは最低水準。本書では、日本の食料自給率の現状を紹介し、農業の衰退、食生活の変化など、自給率が低下した原因を探る。さらに、外国産に頼りすぎる危険性など、食料自給率が低いことによる問題点や、食料自給率を上げるための今後の課題などにも触れる。人間には欠かすことのできない「食」の大切さを、未来を担う子どもたちに学んでもらう一冊。調べ学習や食育にも役立つ。
▼<第1章>「輸入が多くなった日本の食料」 <第2章>「食料自給率を、じっくり見てみよう」 <第3章>「食料自給率は、どのように計算するの?」 <第4章>「食料自給率が下がった原因と問題点」 <第5章>「食料自給率を上げよう!」
●第1章 輸入が多くなった日本の食料
●第2章 食料自給率を、じっくり見てみよう
●第3章 食料自給率は、どのように計算するの?
●第4章 食料自給率が下がった原因と問題点
●第5章 食料自給率を上げよう!
●食料自給率 関連 さくいん
●食品・食材 関連 さくいん
内容説明
先進国の中で自給率が40%と最も低い水準にある日本。食べ物の種類別に詳しく分析し、さまざまな食べ物の自給率と今後の課題をくわしく解説。
目次
第1章 輸入が多くなった日本の食料(国内の食料には、国産と外国産がある;国内の食料のうち国産は約40%(=食料自給率) ほか)
第2章 食料自給率を、じっくり見てみよう(料理別食料自給率1―料理によって、食料自給率はこんなにちがう;料理別食料自給率2―和食は、食料自給率が高いとはかぎらない ほか)
第3章 食料自給率は、どのように計算するの?(食料自給率40%とは「カロリーベース総合食料自給率」のこと;豚肉のカロリーベース自給率は、たったの5%!? ほか)
第4章 食料自給率が下がった原因と問題点(日本の食料自給率は、なぜ下がった?1―食生活が変化したから;日本の食料自給率は、なぜ下がった?2―農業が衰退したから ほか)
第5章 食料自給率を上げよう!(食料自給率を上げると、どんないいことがあるの?;食料自給率を上げるには?1―地元の生産物を地元で消費 ほか)
著者等紹介
生源寺眞一[ショウゲンジシンイチ]
1951年、愛知県生まれ。東京大学農学部農業経済学科卒業。農林水産省の農事試験場や北海道農業試験場の研究員などを経て、東京大学教授。専攻は農業経済学。農学博士。2007年から東京大学農学部長。これまでに食料・農業・農村政策審議会委員(農村振興分科会長・生産分科会長・企画部会長・食糧部会長・畜産部会長など)、「食料の未来を描く戦略会議」座長、日本フードシステム学会会長などを務める。現在は農村計画学会会長、日本学術会議会員、国土審議会委員
深光富士男[フカミツフジオ]
1956年、山口県生まれ、島根県出雲市大社町育ち。企画・編集、執筆、写真撮影などをこなすマルチクリエイター。光文社雑誌記者などを経て、1984年に編集制作会社「プランナッツ」を設立。主に取り組んできた取材テーマは、日本の文化・歴史・食・環境問題(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
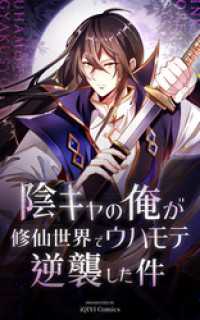
- 電子書籍
- 陰キャの俺が修仙世界でウハモテ逆襲した…



