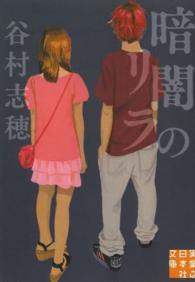出版社内容情報
”カラーセラピー”の効用と実践法を紹介!
エネルギーの「赤」、癒しの「緑」、再生の「青」――なぜ色は人の心に作用するのか? その関係を解明し、カラーセラピーの効用と実践法を紹介!
エネルギーの「赤」、再生の「青」、癒しの「緑」――私たちは日々、”色”からパワーをもらい、”色”で癒されています。「青い海」を見て気持ちが鎮まるのも、「新緑」を見てリラックスするのも、”色”が心に働きかけているから。「色と心」の間には、ふしぎなつながりがあるのです。
▼私たちは、気分や体調にあわせて好きな色を身につけたり、自由に絵を描いたりします。日頃から、色を使って気持ちを表現しているのです。
▼「子どもの絵に暗い色使いが多くなった」「今まで興味のなかった色が気になり始めた」「苦手な色を身につけると、なんとなく体調がよくない」……こんな変化があったら、色が表わす心のサインかもしれません。
▼本書では、「色と心」の関わりをテーマに長きにわたって研究してきた著者が、日頃のリラクセーションや病気のリハビリなど、心のケアに役立つ”色彩セラピー”の効用と実践法を紹介します!
▼『色彩心理の世界』を改題。
[I]色と心のふしぎな関係
[II]色彩心理 ――心の言葉としての色たち
[III]色の“癒し”効果 ――色彩と人間とのかかわり
[IV]色彩セラピーの実践 ――日常に活かす色彩心理
内容説明
好きな色を身につけて元気になったり、自由に絵を描いてスッキリしたり…私たちは日々、“色”からパワーをもらい、“色”で癒されています。「青い海」を見て気持ちが鎮まるのも、「新緑」を見てリラックスするのも、色が心に働きかけているから。本書では、日頃のリラクセーションや病気のリハビリなど、心のケアに役立つ“色彩セラピー”の効用と実践法を紹介します。
目次
1 色と心のふしぎな関係(今日の気分を色で表現すると?;子どもの絵に現れる「無意識」 ほか)
2 色彩心理―心の言葉としての色たち(赤の心理―原初からの叫び;黄の心理―隠された魂に光をあてる ほか)
3 色の“癒し”効果―色彩と人間のかかわり(民族文化の中の色彩;ゲーテに遡る“色彩心理” ほか)
4 色彩セラピーの実践―日常に活かす色彩心理(暮らしの中の色彩セラピー;癒しの力を促すアートセラピー ほか)
著者等紹介
末永蒼生[スエナガタミオ]
色彩心理学者。「色彩学校」主宰。美術活動の傍ら色彩心理の研究を始める。実践の場として1960年代より「子どものアトリエ・アートランド」を開設し、アートによるメンタルケアに取り組んできた。阪神・淡路大震災や池田小学校事件では、ショックで苦しむ子どもたちのための色彩セラピーの活動に関わる。そうした経験から、誰もが使える色彩セラピーの方法を末永メソッドとして体系化。教育、医療、福祉など心のケアを必要とする分野で活用されている。現在は、色彩心理の専門講座「色彩学校」を主宰するほか、講演や執筆活動、色彩デザインやセラピーぬり絵の開発など、色彩心理学の実用化に取り組んでいる。アート&セラピー色彩心理協会会長、多摩美術大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
にがうり
kana
白滝
-
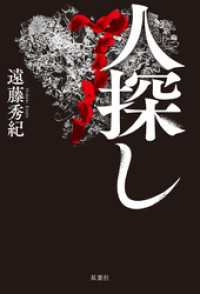
- 電子書籍
- 人探し
-

- 電子書籍
- 死神と銀の騎士 6巻 Gファンタジーコ…