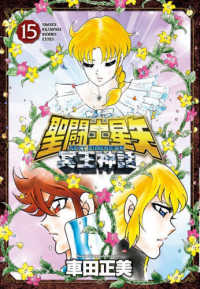出版社内容情報
テレビは愚者のメディアか、賢者の箱か?
「答えはCMの後で」は視聴者を愚弄している! それでも「公共性」を語れるのか? 元NHKプロデューサーが堕落したTVの再生を問う。
タレントを集めてバカ騒ぎ、「答えはCMの後で」の連発、どっちを向いても「韓流」……。このワンパターンは本当に視聴者の要望か? 薄っぺらな「笑い」や「感動」の押し売りは、もうウンザリ! 本書では、元NHKチーフプロデューサーが、テレビが抱える病理に鋭く斬り込む。
▼たしかに、お笑い番組も報道番組も盛況である。ハイビジョンもきれいだ。それでも視聴者の不満と不信が高まっているのはなぜか。なりふり構わず視聴率を追いかける制作者、制度に護られた既得権益への依存、公共性への認識不足などがその背景にある。この国の文化をファースト・フード化させたのは誰か。今こそテレビ文化に対する「慣れと諦め」を超えるべきではないのか。著者はその具体策として、番組審議会の透明化や市民によるメディア・リテラシー活動を紹介する。インターネットが浸透する昨今、果たしてテレビの復権はあるのか。メディアの使命を真摯に捉え直した好著である。
●序章 愚者の箱か、賢者のメディアか
●第1章 「視聴者は神様」はウソだ
●第2章 それでも「公共性」を語れるか
●第3章 いまこそ「品性」を語れ
●第4章 「感動」や「面白さ」を押し売りするな
●第5章 どっちを向いても「韓流」?
●第6章 テレビの「怖さ」とは何か
●第7章 「驕り」を生む風土
●第8章 「志」はどこに消えた?
●第9章 もう「蜜月」の幻想(とき)は終わった――自立する視聴者(1)
●テレビの「掌(てのひら)」で踊らないために――自立する視聴者(2)
●第11章 何がテレビを変えるのか
●第12章 あなたがテレビを見ているのか、テレビがあなたを見ているのか
●終章 テレビは、もういらないのか
内容説明
タレントを集めてバカ騒ぎ、「答えはCMの後で」の連発、どっちを向いても「韓流」…。このワンパターンは本当に視聴者の要望か?薄っぺらな「笑い」や「感動」の押し売りは、もうウンザリ!元NHKチーフプロデューサーが、テレビが抱える病理に鋭く斬り込む。なりふり構わず政治を劇場化させたのは誰か。それでも公共性を語る傲慢さとは。不信と不満が募り、さらにはインターネットの進展から「テレビはもういらない」との声さえ聞こえてくる。果たして再生の道はあるのか。メディアの使命を真摯に捉え直す好著。
目次
愚者の箱か、賢者のメディアか
「視聴者は神様」はウソだ
それでも「公共性」を語れるか
いまこそ「品性」を語れ
「感動」や「面白さ」を押し売りするな
どっちを向いても「韓流」?
テレビの「怖さ」とは何か
「驕り」を生む風土
「志」はどこに消えた?
もう「蜜月」の幻想は終わった―自立する視聴者1
テレビの「掌」で踊らないために―自立する視聴者2
何がテレビを変えるのか
あなたがテレビを見ているのか、テレビがあなたを見ているのか
テレビは、もういらないのか
著者等紹介
立元幸治[タチモトコウジ]
1935年生まれ。九州大学卒業後、NHK入局。主に教養系番組の制作に携わり、チーフプロデューサー、部長、局長などを務める。NHK退職後、大学・短大で「メディア論」や「現代社会論」を担当し、九州産業大学などを経て、2001年東和大学教授を定年で退職。現在は東京工学院四年制大学コース・メディア文学科客員教授を務めつつ、執筆講演活動を展開する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
kinkin
トダ―・オートマタ
wei xian tiang
しめ