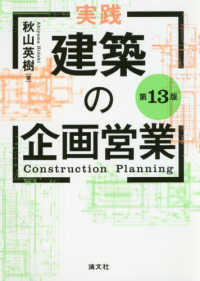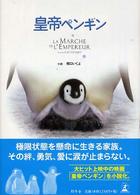出版社内容情報
いまだ息づく「士風」を活写した歴史読み物。
米沢、会津、水戸、長岡、萩、高知、鹿児島……全国各地に伝わるサムライの気風はいつ、どのようにして生まれたのか。
「土佐のいごっそう」とは頑固、偏屈、負けず嫌い。「薩摩のぼっけもん」とは、乱暴者で、かつ放胆な輩。「肥後もっこす」とは、やはり頑固者とか守旧主義の意味。そして「水戸っぽ」とは、理屈っぽく、観念的な人間のこと。いずれも戦国から江戸時代にかけて、その地を治めた殿様(藩)の士風が浸透して生まれた言葉である。一方で、「井伊の赤備え」といわれた精悍な士風(彦根藩)が、幕末には「茶歌凡侍」と笑われるようになった例もある。また、各地の士風はその地勢によって育まれたケースも多い。黒潮の影響で投機的気分を持つ和歌山人、畿内にとっての戦略的要衝である福井藩が持つ現実感覚などが代表例だ。本書は、歴史小説の第一人者が、日本各地に残る「士風」が生まれた由来やエピソードを綴った歴史紀行である。登場するまち(藩)は18だが、いずれも歴史に名を残す人物を生み出したところばかりで、読み応えのある人物評伝にもなっている。
●第1章 鹿児島―示現流なくして薩摩士風なし
●第2章 高知―龍馬を育んだ「いごっそう」の開明性
●第3章 水戸―尊皇攘夷の淵源は「黄門さま」にあり
●第4章 萩―「権力好き」を生んだ防長の地勢
●第5章 和歌山―黒潮洗う地が育んだ投機的気分
●第6章 金沢―いまに生きる「天下の書府」
●第7章 江戸―「明治」を支えた旗本八万騎の底力
●第8章 米沢―寡黙な上杉武士の余風 ほか
内容説明
土佐のいごっそう、肥後もっこす、水戸っぽ、薩摩のぼっけもん…全国各地に伝わるサムライの気風はいつ、どのようにして生まれたのか。代表的な18のまちを巡る歴史紀行。
目次
鹿児島―示現流なくして薩摩士風なし
高知―龍馬を育んだ「いごっそう」の開明性
水戸―尊王攘夷の淵源は「黄門さま」にあり
萩―「権力好き」を生んだ防長の地勢
和歌山―黒潮洗う地が育んだ投機的気分
金沢―いまに生きる「天下の書府」
江戸―「明治」を支えた旗本八万騎の底力
米沢―寡黙な上杉武士の余風
名古屋―豊かで微温的であること
熊本―「肥後もっこす」の光陰
会津―「無私恬淡」を生きる精神風土
福井―越前武士の「現実感覚」
佐賀―合理の地と尚武の地
長岡―強烈な理想主義
彦根―「赤備え」「犠牛」、そして「茶歌凡侍」
広島―生き残った「世慣れたバランサー」
鶴岡―西郷の遺風が流れる地
松代―進出の気象で「教育県」の原型をつくる
著者等紹介
津本陽[ツモトヨウ]
1929年、和歌山市生まれ。東北大学法学部卒業。サラリーマン生活を経て、小説家を志す。1978年、『深重の海』で直木賞受賞。1995年、『夢のまた夢』で吉川英治文学賞受賞。1997年、紫綬褒章受章
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
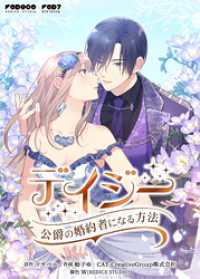
- 電子書籍
- デイジー~公爵の婚約者になる方法~【タ…
-

- 和書
- 全譯王弼註老子