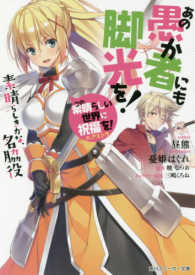出版社内容情報
日本人なら知っておきたい京都・美味の歳時記。
京都に伝わる伝統的な「和」の味とは? 湯豆腐、湯葉、鱧、千枚漬けなど、歴史や調理法を織り交ぜながら紹介した美味礼賛のエッセイ。
「うちは、レールものを買わへん」という祖母の台所哲学によって味感を育まれた著者。いまも“ほんまもん”を求めて「京を食う日々」を暮らす。
▼春には掘りたての筍、夏には鮎や鱧、秋から冬には京野菜の鍋と漬物、さらに豆腐や湯葉や生麩、そして、鮒ずし、鯖ずし、「へしこ」といった発酵食品に舌つづみをうつ。かしこまった京料理におさまらない著者の食欲は、真摯で求道的でさえある。「かつて日本は貧しかったが、食材への気配りは京都だけでなく全国どこの家庭にもあった」と懐かしむ。
▼植物染を専らとし、日本の伝統色と染織史の研究家でもある著者は「料理も染色も基本は同じ」と語る。すなわち「素材を見極める」「時間を見計らって火の強弱を気遣う」という点が同じだという。そして、染色も料理も「早く済ませたいと、どこかで手抜きをすると必ず失敗する」という。滋味あふれる文章と鮮やかな写真が、食への豊かな心を呼び覚ます。垂涎のエッセイ集である。
[第1話]京を食う日々――その一
[第2話]春と夏の舌つづみ
[第3話]京を食う日々――そのニ
[第4話]秋と冬の食欲
[第5話]私の行きつけの店
[第6話]京都人の舌
内容説明
「うちは、レールものを買わへん」という祖母の台所哲学によって味感を育まれた著者。いもま“ほんまもん”を求めて「京を食う日々」を暮らす。春は掘りたての筍、夏は鮎や鱧、秋から冬には京野菜の鍋と漬物、さらに豆腐や湯葉や生麩、そして、鮒ずし、鯖ずし、へしこといった発酵食品に舌つづみをうつ。かしこまった京料理におさまらない著者の食欲は、真摯で求道的でさえある。「かつて日本は貧しかったが、食材への気配りは全国どこの家庭にもあった」と述懐する。滋味あふれるエッセイが、食への豊かな心を呼び覚ます。
目次
京を食う日々
春と夏の舌つづみ
秋と冬の食欲
私の行きつけの店
京都人の舌
著者等紹介
吉岡幸雄[ヨシオカサチオ]
1946(昭和21)年、京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業後、美術工芸分野の出版社「紫紅社」を設立。父没後、生家の「染司よしおか」五代目を継承。植物染を専らとする。伝統色と染織史の研究をおこない斯界の第一人者とされる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さっちも
B.J.
しいら
love_child_kyoto
-

- 電子書籍
- 皇帝陛下のスキャンダル☆ベイビー 逃亡…
-
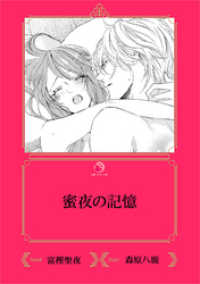
- 電子書籍
- 蜜夜の記憶【イラスト入り】 乙蜜ミルキ…
-
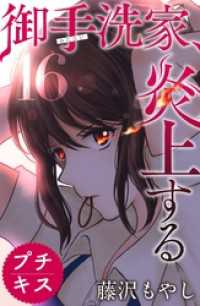
- 電子書籍
- 御手洗家、炎上する プチキス(16)
-
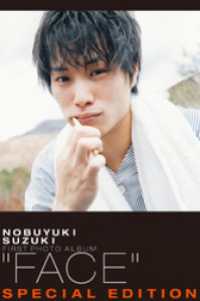
- 電子書籍
- 【完全電子オリジナル版】鈴木伸之デジタ…