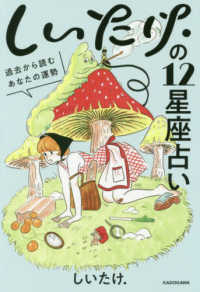出版社内容情報
中国三千年の知恵に学ぶ驚異のテクニック。
月旦をはじめとする観想術や手相術等、古くから鑑定術が発達していた中国。その実践的なテクニックを多くのエピソードと共に解明する。
個人にしろ組織にしろ、成功を望んだり、失敗の落とし穴にはまりたくないのであれば、「人を見抜く眼」が必要不可欠。特に組織において「人を見抜く」という場合、そもそも相手の何を見抜くのか、「人材とは何か」という問いも立ちあらわれてくる。
▼中国古典では、「いかに人を見抜くか」が古来より繰り返しテーマになってきた。現実に密着したリアリズム思考である中国古典にある、人物鑑定法とはいかなるものか?
▼本書は、そんな約三千年にも及ぶエッセンスを抽出し、現代に役立ちやすいように整理を施した一冊である。
▼目次より◎人と組織の浮沈をにぎる人物鑑定◎どんな偉人でも人は見誤ってしまう◎これが、“平時の人材”の見抜き方だ◎乱世・復興期を担う人材のタイプとは◎どうすれば、その人の本当の器がわかるか◎本人にもわかっていない等身大の姿、など。
▼中国古典が教える人の虚飾の剥ぎとり方とは。「できる人」と「できない人」をこう見抜け!
●序章 人と組織の浮沈をにぎる人物鑑定
●第1章 これが、“平時の人材”の見抜き方だ
●第2章 乱世・復興期を担う人材のタイプとは
●第3章 どうすれば、その人の本当の器がわかるか
●第4章 人物鑑定とは、いったい何なのか
目次
序章 人と組織の浮沈をにぎる人物鑑定(どんな偉人でも人は見誤ってしまう;中国兵書のリアリズム思考)
第1章 これが、“平時の人材”の見抜き方だ(波に応じてうつろう人材の姿;平和時の人物鑑定とは ほか)
第2章 乱世・復興期を担う人材のタイプとは(乱世の人物鑑定;復興期に求められる人材)
第3章 どうすれば、その人の本当の器がわかるか(本人にもわかっていない等身大の姿;着膨れした服を取り去る ほか)
第4章 人物鑑定とは、いったい何なのか(楽器は爪弾かないと音色はわからない;熱意と努力、そして自分を知ること)
著者等紹介
守屋淳[モリヤアツシ]
1965年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒。会社勤務を経て、翻訳、書評などの著述業に従事。Web上では「本」のメルマガ、「書評」のメルマガを創刊、編集同人を務めている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 日本医師会の正体 なぜ医療費のムダは減…