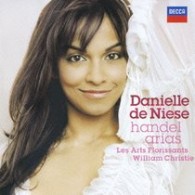出版社内容情報
遺言状を書けば、自分自身の人生が見えてくる。
遺言状は、私たちが自分の意志を完全に表現できる唯一の場であり、生き様が凝縮される。遺言を通して人生を見つめ直す一冊。
友人、知人とのなごやかな団欒の最中に、絶対持ち出してはならない話題がある。宗教の宗派、政治の党派、そして死に少しでも触れるもろもろだ。だから、本書はひとりきりで読んでほしい――と著者は語る。私たちは死の問題を直視するとき、はじめてひとりぼっちの思案にふける。ひとりで他人に相談できない考察を練るとき、人間は本当に鍛えられるものだ。遺言について考えることは、まさに人間鍛錬の場でもあるのだ。
▼また、遺言状を書かない人もいるが、その多くは財産がないからだという。しかし、死んだときに収支を見事にゼロにするほうが至難の業で、何らかの遺産はあるはずだが、その額がたとえ少なくとも骨肉の争いを招く可能性は高い。そうならないためにも遺言状は必要なのだ。
▼本書は遺言状を書くために必要とされる心得と手続きについての手引き書だが、遺言状を通して、現代を生きる人間として知っておくべき「世間学」を説く一冊でもある。
●第1章 日本人の遺言
●第2章 主題は遺産
●第3章 不合理な相続法
●第4章 儀式としての死
内容説明
遺言状は、私たちが自分の意志を完全に実現できる唯一の場であり、その人の生き様が凝縮される場でもある。また、遺言状を書かなかったために、残された者たちがトラブルに巻き込まれることも少なくない。遺言をとおして人生を見つめなおす一冊。
目次
第1章 日本人と遺言(従容として死に就く日本人;多くの人に伝え尊ばれた遺言 ほか)
第2章 主題は遺産(遺言に立ちはだかるもの;なぜ遺言状を書かないのか ほか)
第3章 不合理な相続法(冷たい親子関係と戦後相続法;家族制度の崩壊と家庭崩壊 ほか)
第4章 儀式としての死(俗なるもの、ソーシキ・ハカ・戒名;辞世がなぜ必要だったのか)
著者等紹介
谷沢永一[タニザワエイイチ]
昭和4年大阪市生まれ。昭和32年関西大学大学院博士課程修了。関西大学文学部教授を経て、平成3年退職。専門は書誌学、近代日本文学。評論家としても多方面で活躍。現在、関西大学名誉教授。サントリー学芸賞、大阪市民表彰文化功労、大阪文化賞受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書
- LA BATTUE