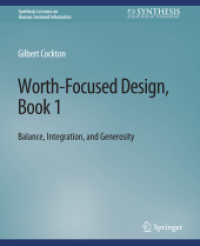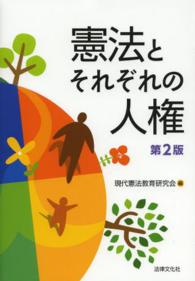出版社内容情報
伝統と宗教感覚の喪失で彷徨する日本人の魂。心の拠り所となる自然観、人間関係、社会のあり方を先人の生き様・智恵から再発見する。
いま日本人は自らの「心」の在り処を見失いつつある。何に感動し何を悲しみ、日々をどう生き、死に際して何を考えたのか。この国に連綿と繋がる感性を取り戻す事が強く求められている。
▼本書では「日本人の信仰のかたち」を見つめてきた著者が、人々の感性を掘り起こしていく。
▼西行、芭蕉という「日本をさまよう」求道者がいた。彼らは蔑まれ孤独の中に生きる「こじき」に憧れ、そうなる事で悟りを開こうとしたのだ。つまり私を無の状態にしたとき、ものがよく見えてくると信じ、そういう心の在り方、生き方にどこまでもこだわった、と著者は言う。また日本には「人間は一度死を通過する事で神になることができる」という独自の死の感覚があり、そこから死の世界の近くにいる「老人」が神にも等しい存在として崇められてきたのである、と述べていく。
▼日本人の行動規範をユニークかつ大胆な視点から論じていく、眼からウロコが落ちる日本人論。
[1]神と仏と日本人
●「鎮守の森」は泣いている
●それでも「鎮守の森」は泣いている
●カミの再生へ
[2]日本精神の深層
●もう一つの「日本教」
●日本人の心情
●野性的「武士道」の精神
●遺伝子時代の「生老病死」観
内容説明
この国の人々は、何を信じて生き、死んでいったのか。本書は、これからの日本におけるデモクラシーの可能性を、神仏信仰という多神教的な風土、すなわち「鎮守の森」の風土のなかで追求したものである。
目次
1 神と仏と日本人(「鎮守の森」は泣いている;それでも「鎮守の森」は泣いている;カミの再生へ)
2 日本精神の深層(もう一つの「日本教」;日本人の心情;野性的「武士道」の精神;遺伝子時代の「生老病死」観)
著者等紹介
山折哲雄[ヤマオリテツオ]
1931年生まれ。東北大学印度哲学科卒業、同大学大学院博士課程単位取得退学。東北大学文学部助教授、国立歴史民俗博物館教授、国際日本文化研究センター教授、白鳳女子短期大学学長を経て、現在、京都造形芸術大学大学院長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
- 洋書
- Existenz...