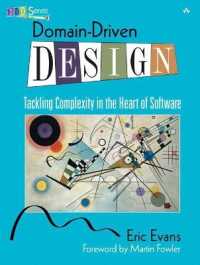出版社内容情報
沈黙する学生達や、「アアセヨ・コウセヨ」という標語・放送の氾濫と戦う一哲学者が、言葉を軽んじ対話を封じる日本の言論風土を分析。
内容説明
「何か質問は?」―教師が語りかけても沈黙を続ける学生たち。街中に溢れる「アアしましょう、コウしてはいけません」という放送・看板etc.なぜ、この国の人々は、個人同士が正面から向き合う「対話」を避けるのか?そしてかくも無意味で暴力的な言葉の氾濫に耐えているのか?著者は、日本的思いやり・優しさこそが、「対話」を妨げていると指摘。誰からも言葉を奪うことのない、風通しよい社会の実現を願って、現代日本の精神風土の「根」に迫った一冊である。
目次
第1章 沈黙する学生の群れ
第2章 アアセヨ・コウセヨという言葉の氾濫
第3章 「対話」とは何か
第4章 「対話」の敵―優しさ・思いやり
第5章 「対話」を圧殺する風土
第6章 「対話」のある社会
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やすらぎ
134
対話もなければ対面もなくなった現在。対話とは自らの体験、実感、価値観に基づいて率直に語ること。1997年の新書。作者はなかなか厳しめです。…今考えていることを話す。目の前の明らかな間違いには、躊躇なく発言する。それができないんです。…なぜ今、私はこれをしたいのか。この読書に何を感じるのか。そう感じたのはなぜか。その先に求めるものはなにか。…自身を見つめ、表現する力は、作者には到底及びませんが、少しは備わったかもしれません。…私はこうありたい。だからこうしたい。まずは相手を尊重することから対話は始まります。2020/06/13
団塊シニア
60
いじめについて言及しており、いじめっ子以上に悪質な加害者、それはいじめをみてみぬふりをする多くの子供たちだと断言している、17年前の執筆であるが、いじめの実態がいまだに変わらない現実は悲しい。2014/10/27
活字スキー
30
【だからこそ、私は無力な言葉をさらに無力にしたくはない。言葉のもつ一抹の「威力」を信じたい】大学でドイツ語と西洋哲学を教える著者による〈対話〉のススメ。一~二章での著者の実体験は、優しくないことと空気を読まないことにかけてはそこそこ自信のある自分から見ても「なかなか厄介なじーさんだな」と思わされたが、後半は現在も日本に蔓延する深刻な病に対する啓蒙の書として刊行から20年以上経っても読み応え十分。会話と対話の違い。他者との差異、対立があってこその対話。対話のない社会には「他人」がいない、「自分」もいない。 2021/09/07
速読おやじ
26
全体を通してエキセントリックな主張に思えなくもないが、日本人とは、ああその通りだなと納得する事多数。対話、対立を避ける事が美徳とされる。思いやりは実は利己主義の変形=自分の身を守る事が先決。山本七平の「空気」にも言及していたが、誰からも不平不満が出ない、誰にも言わせない事が最高の目標とされる。竹内靖雄はこれを状況功利主義という。様子を見る、こうするより他に仕方ない、、あーこんな事言ってるわ。。和を以て尊しという聖徳太子の精神は対話を避ける事では無かった筈。対話、対立の向こう側にあるものを追求せねば。2019/05/17
さきん
26
「何か質問は?」―教師が語りかけても沈黙を続ける学生たち。街中に溢れる「アアしましょう、コウしてはいけません」という放送・看板etc.なぜ、この国の人々は、個人同士が正面から向き合う「対話」を避けるのか?そしてかくも無意味で暴力的な言葉の氾濫に耐えているのか?著者は、日本的思いやり・優しさこそが、「対話」を妨げていると指摘。誰からも言葉を奪うことのない、風通しよい社会の実現を願って、現代日本の精神風土の「根」に迫った一冊である。2016/08/20
-

- 電子書籍
- 氷の城壁【タテヨミ】 75 マーガレッ…