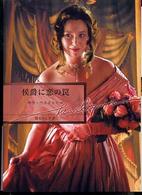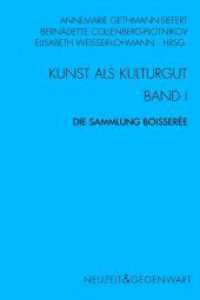目次
彩飾写本とパリの古本屋巡り
五六〇年前の本
魔がさした教授と誤解した教授と間違えた教授
十四世紀の聖書の一葉
彩飾写本の生まれ故郷
ケンブリッジのパーカー図書館
ベラルド君
彩飾写本の旅
カタルーニャの中世美術
アメリカにおける美術の思い出
パリのカルチャーショック
フランドル絵画が辿った数奇な運命
青木繁の少女の「おもかげ」
著者等紹介
内藤裕史[ナイトウヒロシ]
1932年東京都生。1960年札幌医科大学卒業。1964~67年米国エール大学付属病院麻酔科研修医。1969年札幌医科大学助教授。1971~72年米国エール大学薬理学研究室研究員。1976年筑波大学教授。1995年4月茨城県立医療大学副学長、筑波大学名誉教授。2001年3月茨城県立医療大学退職。2004年4月「中毒学の確立」により吉川英治文化賞受賞。財団法人日本中毒情報センター理事
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヤクーツクのハチコ
2
彩飾写本の世界、ではなくて彩飾写本にはまった僕の世界、だったけれど。エッセイ集だね。普通のガイドブックには載ってない教会附属の美術館や図書館の情報がのってるから、中世美術めぐり旅行をしようとしてる人にはお誂えかな2012/10/08
まめはち
1
国立西洋美術館の内藤コレクションが忘れがたく、コレクターご自身について知りたくて手にした一冊。興味深かったのは、彩飾写本には贋作がないこと、作者不明でも価値に関係はないこと、切り離された一枚物も、不完全な写本も高価であること。羊皮紙は羊の胎児の皮であること。それにしても、「無名でも美しいものは美しいと認識できる」あるべき美術鑑賞がこうした写本では可能だから不思議。祈りを込めた精緻な筆致が目をとらえて離さない。内藤氏のコレクションが国立西洋美術館に収蔵されて本当に良かった。また足を運びたいと思う。2020/08/05
Toshi
1
先日国立西洋美術館で見た「内藤コレクション」の内藤先生の著書。解説書と言うよりかは、自身の写本との出会いから、世界を巡るコレクションの旅、各地の美術館の訪問記からなるエッセー集。内藤先生は筑波大教授も務めた日本を代表する中毒学の権威であるらしいが、本人曰く、「自分の人生で医学にかけた情熱と、美術にかけた情熱をくらべると、労力も、時間も、お金も、美術がはるかに上回る」とのことで、その熱量が伝わってくる一冊。2020/02/03
ヒラタ
1
著者はお医者さん、医学への情熱と同等以上の彩飾写本へのあつい思いが、伝わります。ーミニアチュールという語は朱色の顔料として使用した辰砂(ラテン語でminium)に由来、細密画と訳されているが、小さいことを意味するminiとは関係ないとのことー第二部はアメリカに留学した時に訪ねた美術館の話など、莫大な富で集められた芸術品のこと。なかでも私の注意をひいたのはイサベラ.スチュワート.ガードナー美術館のこと、感想は書かれてはいませんでしたが、留学していた年代から察するにまだフェルメールは盗まれていない。2013/11/05
-

- 電子書籍
- キュロス~死すべき運命の王子【タテヨミ…
-

- 和書
- 利休七哲