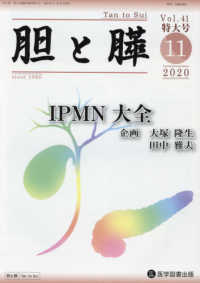内容説明
戦前に計画された紀元二六〇〇年博と1970年の大阪万博EXPO’70を結ぶ、都市計画家、建築家、そして前衛芸術家たちの、終わりなき「未来」への夢の連鎖のなかに「環境」の起源をたどるタイムトラベル的異色長編評論。
目次
第1章 「爆心地」の建築―浅田孝と“環境”の起源
第2章 一九七〇年、大阪・千里丘陵
第3章 「実験(エキスペリメンタル)」から「環境(エンバイラメント)」へ―万博芸術の時代
第4章 ネオ・ダダとメタボリズム―暗さと明るさの反転
第5章 戦争・万博・ハルマゲドン
第6章 そこにはいつも「石」があった
第7章 ダダカンと“目玉の男”
第8章 万博と戦争
著者等紹介
椹木野衣[サワラギノイ]
美術評論家。1962年秩父市生まれ。同志社大学文学部卒。多摩美術大学美術学部助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
サイバーパンツ
11
近代化が未完のままに終わり、蓄積なき忘却と悪しき反復を繰り返す日本の芸術文化の状況を「悪い場所」であると『日本・現代・美術』の中で著者は批判したが、本書では、かつての聖戦芸術(戦争画)から万博芸術を経てジャパニメーションに至るまで、三度も反復される国策芸術の系譜を読み解くことで前著の「悪い場所」論を補完する。本書が出版された頃とちょうど同じ時期に、戦時下に育まれた日本のまんが・アニメ文化が、クールジャパンとして国策化されることに反発した大塚英志とも問題意識を共有するような内容だった。2019/05/20
takao
2
ふむ2024/02/10
Mentyu
2
美術史と美術評論の立場から、大阪万博を問い直すというのが本書の意図するところ。その分析対象は、関わった芸術家・建築家から、やがて関東大震災、日中・太平洋戦争、満州国、敗戦へと広がり、万博そのものが幾多の壊滅を繰り返す戦争の文脈に由来すると結論づける。敗戦からの完全な復活を、それ自体が帝国主義に由来する万博会場で宣言することで「輝かしい未来」を新たな植民地としたという分析はなかなか興味深い。同時にそれが、会期終了と共に無人となるのを運命づけられた「未来の廃墟」だったというのも痛烈な皮肉である。2017/10/15
しまりんご
2
関東大震災、第二次大戦、万博を、日本史・芸術史における重要なポイントとして選び、論を展開。刺激的で勉強になる部分がある論文だが、すいすいと流れるような言葉の中で論理の飛躍もかなりあると感じた。2015/04/18
ひろ
1
大阪万博は戦争からの復興の象徴としてではなく、都市・テクノロジーの実現と廃墟化という点において原爆の爆心地における表象不可能性を一面で表していた。一方でその国家的計画に携わった美術家・建築家、そう岡本太郎ですらもその直進性には抗えなかった。磯崎新をして「戦争に荷担したようだ」とまで言わしめるものがあった。そうなのだろう。ただ「現代とは既に核戦争後の世界だ」とまで言い切るのはどうか。個人史からくる心証、歴史的事実、批評がない交ぜになっており、正直通読して浮かび上がる何かがない。2022/02/01