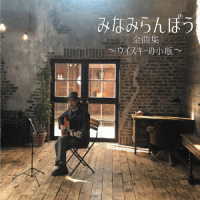内容説明
本書の半分は、新しい知識を、他分野の研究者だけでなく、一般の読書人にも伝えるべく、できるだけ平易な言葉で述べた。本書の半分では、たんなる知識の伝達ということを越えて、気候と他の分布現象との関係を論じている。
目次
1 世界の風系(赤道西風帯;亜熱帯高圧細胞 ほか)
2 世界の気候と人間(物に及ぼす気候の影響;人間への影響)
3 日本の気候区分(動く気候の図的表現;気候区の大きさ)
4 日本の気候と他の分布現象(動植物の分布と気候;人間生活と気候 ほか)
著者等紹介
鈴木秀夫[スズキヒデオ]
1932年神奈川県に生れる。1955年東京大学理学部卒。現在、清泉女子大学教授、東京大学名誉教授、理博
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
RED FOX
11
「もっとも基本的な位置関係はヒマラヤ・チベット山脈の風下という位置にあたることである」日本の梅雨、気候区分の多さの源の一つにヒマラヤの影響との事。温度差、湿度差、地表の風、地球が生き物に思える。2025/04/07
くまくま
6
もはや古典の領域に達しており、現在のデータや昨今の異常気象を鑑みる必要がある。しかし、気候学の基本視点を学ぶための入門書としての価値は現在でも色褪せてないはずである。2019/10/24
Kiro
0
相関関係や因果関係は、どれだけ納得するかの問題であるみたいな話。例えば、気候区分と植物分布の相関関係認められるのに、気候区分と離婚率の分布は人間は簡単には認めたくない。「雪が降る地方の家は間取りがこうなってて、だから家族関係がこうで、離婚率がどう」という中間項が入ると納得しやすい。ただし論理構造的に進歩していない場合が多い。あと面白かったのはベルグマンの法則とアレンの法則の話。顔の彫りが浅いのとか足が短いのって、熱を体外に逃さない工夫なのね。2020/02/12
-

- 電子書籍
- Running Style(ランニング…
-

- 電子書籍
- 自由主義時代の子どもたち 単行本版 1…